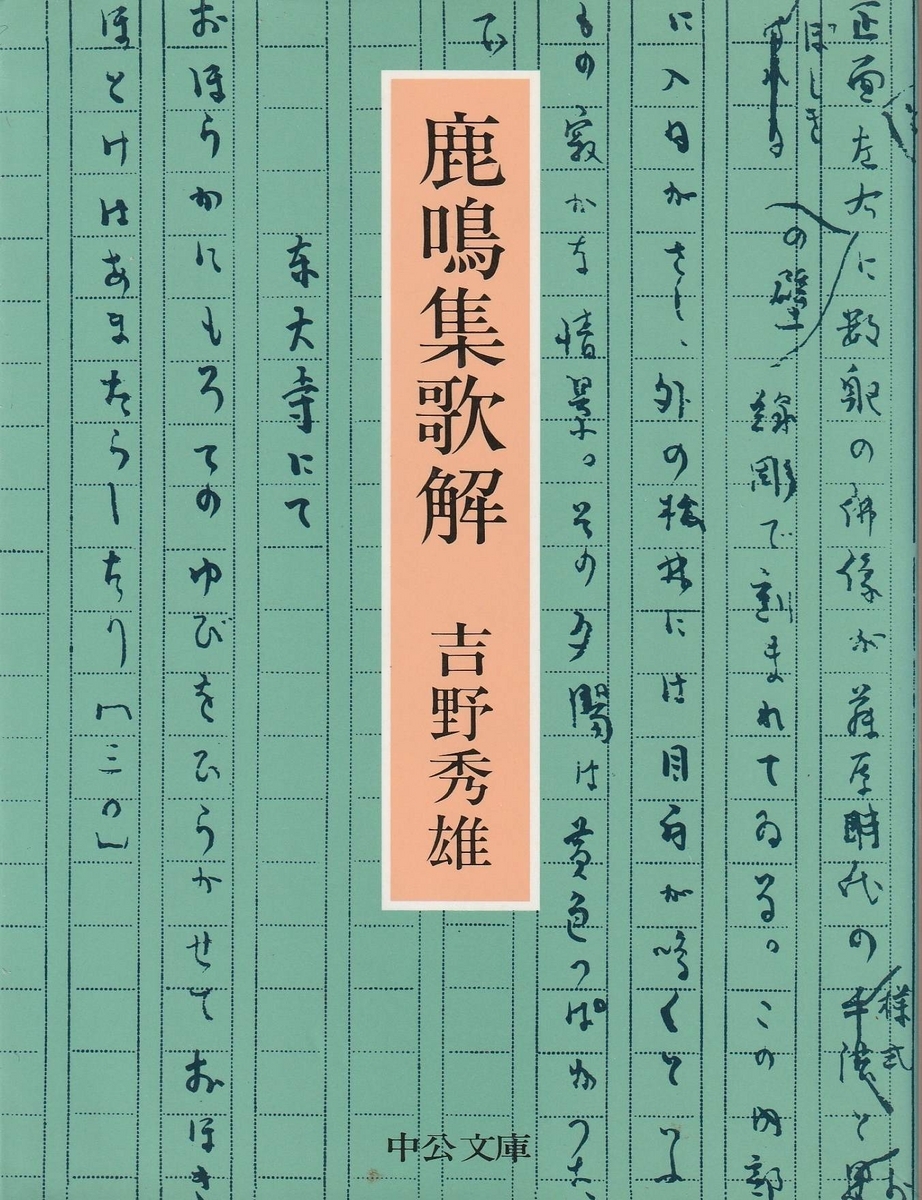
吉野秀雄『鹿鳴集歌解』(中公文庫 1981年)
体調がすぐれず、少し間が空いてしまいました。この歳になると、何かと故障が出てきますので、ブログ公開をお休みすることもこれから起こると思いますが、ご了承ください。今のところ、0と5のつく日に、アップするようにしていますので、もしブログ内容が更新されていなければ、次の回までお待ちいただければと思います。
で、体調不良の結果、楽しみにしていた22日の奈良日仏協会の催しに参加できずになりました。会津八一についての講演を聞いた後、会津八一の歌碑のいくつかを見て回るという企画で、準備として、会津八一に関する本二冊に加えて(9月25日記事参照)、この本を読みかけていたので、残念でした。
この本は、会津八一の弟子である吉野秀雄が、師の『鹿鳴集』のなかの奈良に関する歌に注釈を施したものです。もともと会津八一の歌は平明なものが多いように思いますが、見た目は平明でもなかなか奥深いということが、注釈でよく分かりました。以前も書きましたが、俳句や短歌は、少し説明があったほうが理解が深まる気がします。それは短詩型ジャンルの瑕疵ではなく、俳句や短歌が短い分目立つだけで、小説や音楽、美術作品にも共通するものだと思います。
吉野秀雄の注釈は、語彙が豊富かつ、歌に対する情熱、師に対する敬愛にあふれたもので、説得力があります。とくに注釈をしめくくる最後の一文が印象的です。また師に接していた弟子ならではの情報もありました。いくつか例を引いてみますと、
かすがのにおしてるつきのほがらかにあきのゆふべとなりにけるかも・・・この歌、想は単純だが詩魂充実して余りあり・・・道人の歌は、柔艶にしてしかも骨法を得、総じては温もりとうるほひを湛へる完成感の密度において妙境を顕示するものといへよう/p15
〔二〕(かすがののみくさをりしきふすしかのつのさへさやにてるつくよかも)では鹿が臥したが、〔三〕(うちふしてものもふくさのまくらべをあしたのしかのむれわたりつつ)では作者自らが臥してゐる。道人はその巨躯をいかにもものうげにそこいらの草原などに横たへる習癖をもってをられることを私は知ってゐる/p17
くわんおんのしろきひたひにやうらくのかげうごかしてかぜわたるみゆ・・・作者はほの白い額に揺らぐ繊細な瓔珞の影によって観音像の生きのいのちを捕へようとしてゐるのだ/p28
たびびとにひらくみだうのしとみより迷企羅(めきら)がたちにあさひさしたり・・・この歌、メキラの音がキラキラ・キラメクなどに通ずる陽性のものであり、且つ迷企羅の提げる太刀であるといふところで、いかにも朝日のさすにふさはしい/p35
あめつちにわれひとりゐてたつごときこのさびしさをきみはほほゑむ・・・「われ」は一応作者自身には違ひないが、また像(夢殿の救世観音)そのものでもある・・・これは道人の絶唱の一つであるが、その魅力の因って来るところは、作者のいのちが救世観音のいのちに渾然融けこんでゐる点にあるものとせねばならない/p81
さきだちて僧(そう)がささぐるともしびにくしきほとけのまゆあらはなり・・・「くしき」はこの弘仁仏の神怪にして艶媚な印象を総括していったもの。つまりその美は、暗く隠れた薄気味悪い肉感的なそれであるのだ/p93
みほとけのひぢまろらなるやははだのあせむすまでにしげるやまかな・・・端麗で荘重で、名状しがたい肉感を漂はせてゐる。「やははだのあせ」と「しげるやま」の微妙な感覚の関連による歌である/p99
さくはなのとはににほへるみほとけをまもりてひとのおいにけらしも・・・この像(聖林寺十一面観音)の永遠美と僧の衰老のさまが対比されてゐるわけだ/p158
この本を読んで、前回引用した以外に気に入った歌は次のとおり。
ふじはらのおほききさきをうつしみにあひみるごとくあかきくちびる/p53
からふろのゆげのおぼろにししむらをひとにすはせしほとけあやしも/p58
すゐえんのあまつをとめがころもでのひまにもすめるあきのそらかな/p69
ひとりきてめぐるみだうのかべのゑのほとけのくにもあれにけるかも/p82
いにしへをともらひかねていきのをにわがもふこころそらにただよふ/p113
しかなきてかかるさびしきゆふべともしらでひともすならのまちびと/p133
いかでわれこれらのめんにたぐひゐてちとせののちのよをあざけらむ/p143
たちいればくらきみだうに軍荼利(ぐんだり)のしろききばよりもののみえくる/p166
ひかりなきみだうのふかきしづもりにをたけびたてる五大みやうわう/p167
なかでは、上記のp53とp58の歌のところで、光明皇后を模したと言われる法華寺の十一面観音像にまつわる伝説と、光明皇后が法華寺の蒸し風呂で人びとに施浴を行なった伝説が紹介されていたのが、面白く思いました。光明皇后が、願をかけて千人の垢をこすったが、最後の一人の瘡だらけの病人から、この瘡の膿を吸い取れば病は治癒すると言われたので、皇后は病人の全身の瘡を吸い、そして、「后病人に語って曰く、我汝が瘡を吮(す)ふ、慎みて人に語ること勿れと。時に病人大光明を放ち、告げて曰く、后は阿閦仏(あしゅくぶつ)の垢を去りぬ、又慎みて人に語ること勿れと」(p57)とありました。病人は仏の化身だったわけですが、これはまさしく西洋にあるような聖人の奇蹟譚ではないでしょうか。