
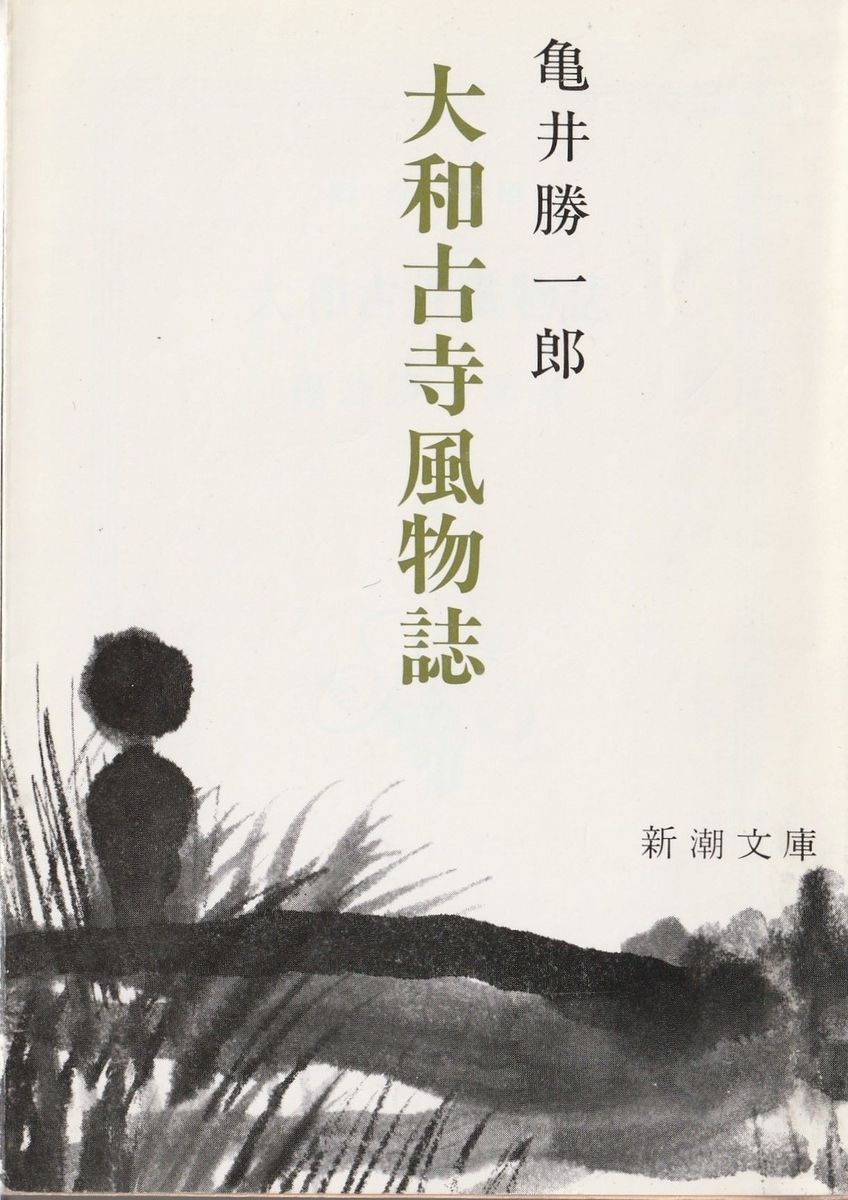

和辻哲郎『古寺巡礼』(岩波文庫 1986年)
亀井勝一郎『大和古寺風物誌』(新潮文庫 1997年)
龜井勝一郎『改訂増補 大和古寺風物誌』(養徳社 1946年)
奈良に関する本の続きで、古典的二作品を読んでみました。『古寺巡礼』は会津八一や堀辰雄も影響を受けたと思われる先駆的著作(初版1919年)、『大和古寺風物誌』は、初版1942年でそれより新しいですが、奈良の古寺に触れる場合、よく言及される作品です。改訂増補版には、新潮文庫版にない「君臣相念」、「帰依と復活」の2小品と、写真数点が収められていました。
二作に共通して感じられるのは、情熱的な筆致。彼ら二人に限らず、戦後間もないぐらいまでの学者、評論家には、専門知への激しい渇望があるように思えます。絶対的な価値への信仰とでも言えばいいでしょうか。それを極めようと、とことん勉強し、自ら考え抜こうとしています。逆に、意にそぐわないものに対しては徹底的に戦おうとする気持ちが垣間見えます。戦後世代の我々は、どこかで相対主義の洗礼を受けたらしく、漫然とした知識を振りまくだけの体たらくとなりました。
和辻哲郎と言えば、読む前から、哲学者然とした冷たい印象を受けていましたが、この本を読む限りは、自分の感覚を大切にしそれを土台にして考察する姿勢が感じられました。さらに、巻末の「解説」に紹介されていた和辻自らが削除したという部分を読むと、感激の言葉が生々しく書かれていたので驚きました。「解説」の筆者谷川徹三の「和辻さんの学問を豊穣にしたものが、ほかならぬ、その学者として和辻さんが拒んだものであった」(p278)という指摘はまさにそのとおりと思われます。
亀井勝一郎も、情感たっぷりな記述で、美と信仰への若々しい考察が繰り広げられています。冒頭から、聖徳太子への崇敬に満ちた言葉が連なり、最後には、聖武天皇が民を撫でるように愛する気持ちを思いやるなど、上代の天皇のあり方への共感が溢れていました。また章の終わりに万葉風の自作の長歌が添えられたりしています。
細かい点ですが、ほかに二人に共通してあったのは、本来は中性の仏像を女性と捉える見方で、和辻のアジャンター壁画について書かれた部分での「天人や菩薩として現わされた女の顔や体の描き方」(p19)という表現や、聖林寺十一面観音の「露わな肌が黒と金に輝いて・・・肉づけは豊満」(p63)、薬師寺金堂の「脇立ちの・・・柔らかくまげた右手と豊かな大腿との間から、向うにすわっている本尊薬師如来の、『とろけるような美しさ』を持った横顔」(p157)などいたるところにそう思わせるような記述があり、亀井も、中宮寺思惟像について、「清純な乙女を彷彿せしむる・・・豊頬をもつ美少女のごとく、口辺には微少すら浮べ」(p85)とか書いていました。
二人の違いは、と言えば、情熱的と言ってもやはり和辻哲郎には、インド、ギリシア、中国の芸術との関係を探ろうとしたり、古寺にとどまらず、仮面、猿楽、蒸し風呂についてまで筆が及ぶなど、興味の範囲が幅広く、ものごとを論理的に考えようという姿勢が強く感じられるのに対し、亀井勝一郎のほうは、当時の世情や政治的背景に思いを馳せ、天皇や当時の人々に寄り添おうとする、素朴で宗教的な心情が中心になっているのが感じられたことです。
なので、和辻が「われわれがある仏像の前で、心底から頭を下げたい心持ちになったり、慈悲の光に打たれてしみじみと涙ぐんだりしたとしても、それは恐らく仏教の精神を生かした美術の力にまいったのであって、宗教的に仏に帰依したというものではなかろう」(p37)と言うのに対し、亀井は、「仏像は語るべきものでなく、拝むものだ」(p206)と書いています。
二冊のなかで、印象深かった論点を簡単に書いておきます。『古寺巡礼』では、
①仏教でもキリスト教でも、当初は、芸術とは結びつかず、むしろ芸術を感性的な性質を持つものとして排斥する立場にあったと指摘したうえで、芸術が人の精神を高め心を浄化する力を持つことは、無視さるべきではないとしている。
②民族によって、理想の顔や体格がどう変わって来るかは、文化の伝播と連関して興味のある問題として、仏像の顔立ちが蒙古系の顔をしているとか、仏像が身につけている武具がどこの国のものかとか、仏画が東へ来るほど清らかに気高くなっているのは仏教の教義の変遷と関係があるかと、詮索している。
③仏教の教義と、描かれた形像や風景との乖離について考えているところ。例えば、菩薩は人ではないが、人体を借りて表現され、神的な清浄と美を纏わせることによって、超人らしさと人間らしさを結合させているということ。また観無量寿経で示されている浄土は、宇宙的な規模のもので、とうてい絵に表わすことができず、音楽でぐらいしか表現できないものだが、当麻曼荼羅ではその浄土を描いていて、現世の享楽を無限に延長しようとしたものだとこき下ろしている。
④Y氏から聞いた古墳の盗掘の話:盗掘者が古墳の蓋をあけると、中には色の白い美しい女が、まるで生きたままの姿で横たわっていた。しかし、男が仰天して尻餅をついている間に、女の姿は変色してハラハラと灰のように砕けてしまった。→まるで吸血鬼映画の結末のようなシーン。
『大和古寺風物誌』では、
①茶碗にせよ、信仰、思想、恋愛の上のことにせよ、比較において味わうという態度には、近代人の致命的な弱点がひそんでいるとし、「比較しつつ信仰する人間の信仰を信用できるだろうか、比較しつつ愛する人間の愛情を信じうるだろうか」(p44)と問いかけているところ。知性は博物館の案内者としては実に適任だが、信仰の導者としては「無智」が必要だとしている。→バタイユの「非知」を思わせるが、すべてにおいて無智である訳には行かないだろう。
②仏像が美術品であるか、信仰の対象であるかについての議論。「仏像は一挙にして唯仏であった・・・一切を放下せよというただ一事のみを語っていたにすぎなかったのである。教養の蓄積というさもしい性根を、一挙にして打ち砕くような勁(つよ)さをもって佇立していた」(p64)という言葉で、結論を示している。そして「古仏を美術品として鑑賞に来る教養ある人々の勿体ぶった顔にながし眼を使う」(p66)寺の立場の難しさについて語っている。
③伝説のすべてを迷信とする考え方は誤りで、そういう言い伝えのなかに、民心に宿る愛と信仰とがはっきりと顕れている、としているところ。
④法隆寺夢殿の救世観音の中性性から、「タヒチでは女性が男性的、男性が女性的なところがあり両者が近似しているので、男女関係が罪悪の観念のない安らかなものとなっている」というようなゴーガンの文章を連想して、ゴーガンは東洋の涅槃を見たのではないか、と書いている。
⑤ハイネの『伊太利紀行』の記述:ハイネが、廃墟の上に座り夢みているが高貴な面影を失わないイタリア人を見て、「観光地として訪れる漫遊の客人達は、たとい純白の高価なシャツを身につけ、すべてを現金で景気よく支払っても、この伊太利人に比べるなら一個の野蛮人にすぎぬ」(p38)と洩らしている言葉。
⑥夕暮や夜の古寺が最高だという。「夕暮の塔をはるかに慕いつつ、やがてその下に立って月夜の姿を仰ぐまでのこの時間を、私は人生の幸福とよんでもいい。少なくとも私の半生において最も幸福な刹那であった」(p142)。
前回、会津八一の真似をして、秋篠寺から生駒山を振り返って見ると書きましたが、秋篠寺の南門を出たところでは、樹々や建物で遮られて見えませんでした。近くの人に生駒山の見えるところは?と尋ねると、少し先まで歩かないと見えないと言われたので、諦めました。