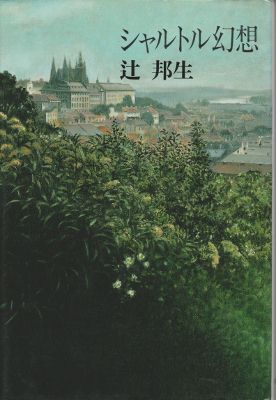 ///
///

辻邦生『シャルトル幻想』(阿部出版 1990年)
辻邦生『のちの思いに』(日本経済新聞社 1999年)
辻佐保子『「たえず書く人」辻邦生と暮らして』(中公文庫 2011年)
高校生時分におそらく友人に薦められてと思いますが『夏の砦』を読んだことを覚えています。水色の花柄(だったかな?)の箱の印象も洒落た感じだし、タピストリなんか初めて聞く言葉も出てきて(たように思う)、それまで読んでいた日本の小説とは少し違った何か新しいテイストを見つけたように感じ、続けて『廻廊にて』などを友人らと競うようにして読んだおぼろげな記憶があります。今回『シャルトル幻想』を手に取ったのは、フランスへの旅でシャルトルへ行くつもりだったので、何かの参考になるかと思ったからですが、タイトルにもなっている「シャルトル幻想」は7ページ弱の短編であまり参考にはなりませんでしたし、結局はシャルトルにも行かずじまいでした。でも、この本に収められていた他の作品がなかなか面白かったので、続けて本棚にあった辻邦生関連本を続けて読むことになりました。
『シャルトル幻想』は辻邦生の初期短編を集めたもので、むかし別の形で読んだことがあったかもしれませんが、まったく覚えていません。残念ながら、初期の短編集『異国から』、『城・夜』、『北の岬』なども今は手放してしまっていて、確認もできませんでした。
収められている作品は、ひとつは体験手記、もうひとつは物語と、大きく分けて二つの傾向があります。双方ともに精神性が大きく支配していて、物語にも観念小説的な構造があるように思います。例えば「ある晩年」では「秩序」、「影」では「見通す」という言葉がキーワードになって、物語が展開されています。これは、『のちの思いに』のなかで、若い頃に埴谷雄高に憧れたことが書かれていましたが、その影響でしょうか。
なかでは「献身」がもっとも迫力が感じられました。一言でいえば、詩を捨てた後のランボーの物語です。ランボー自身の独白、妹の独白、それに客観的な叙述が入り混じり、その転換が文の途中に突然行われたりしますが、語りの力が横溢しているので、不自然さは感じられず、人物像が動き出すようです。見方を変えれば、パリ・コミューンが詩人の核になっているというランボー論を小説の形で示したものと言えるでしょう。
「ある晩年」と「影」はどこか共通するところがあって、若干習作的なにおいはするものの、やはり文章の力がすばらしい。「ある晩年」は、人は良く描けているのに、理屈っぽく書き込みすぎているところが惜しい。愛人の息子が5歩ほど離れたところで、工事現場からレンガが落ちてきて死に、それによって愛人は発狂、幸せな団欒がめちゃくちゃになるという展開のなかで、「あの日焼けした青春そのもののようなクリストファと、この沈黙した石の列。その間はほんの五歩もはなれていないのに、それを距てる距離は無限なのだ。この墓地の沈黙が本当なら、人生なんて、どんな楽しげに、陽気に、活力にみちて廻っていても、それは見せかけの、いつわりの姿にすぎないのではないか」(p127)、「これが運命という抗しがたいものの、眼に見える瞬間なのかもしれない」(p146)といった運命についての嘆きが北国の町の寂しい風景とともに語られます。「影」は、精神が錯乱していく表現主義映画的な人物描写が印象に残りました。
『のちの思いに』は、最晩年に生涯を振り返って書かれた自伝で、日本経済新聞の「私の履歴書」として連載され結局絶筆になったもの。大学時代の勉学とアルバイト、佐保子夫人との出会い、その後のパリ留学生活が描かれています。
東京大学に入学して、並み居る秀才たちに圧倒されながら、浅草の劇場に出入りするあたりは、伊豆の踊子と永井荷風の生き方とを合わせたような話か。辻邦生は勉学とアルバイトに励みながらも、最初からはっきりと小説家を志望していたことが分かりました。さらに『「たえず書く人」辻邦生と暮らして』を読んで、小説家としてはおくてで、いろいろと試行錯誤し煩悶していたことも分かりました。
どうも下世話な興味ばかりに目が行くようですが、渡辺一夫がかなりな酔っ払いだったり、森有正が下着を洗わずにほっておいたり、斎藤磯雄が「まだシャンゼリゼは華やかですな」と感にたえたように言ったりと、大先生たちが生身の人間として描かれていて、半分崇高さが減じたように思えますが、これがまた面白い。
またこの回想を読むと、辻邦生の若い頃と私たちの世代とでは、何か大きく違っているところがあることが実感できました。それは、戦後まもなくの大学には戦前の教養主義的雰囲気や、社会の上流で生きる使命感といったエリート意識がどこかに残っているように見えるのに対して、我々の時代には、社会の価値観を拒否する反あるいは非社会的な空気が蔓延していて、どこか捨て鉢な気分があったことです。
『「たえず書く人」辻邦生と暮らして』は、辻邦生が亡くなった後、佐保子夫人がもう一度夫の創作を読み返しながら、昔の思い出を綴ったものですが、ある種創作のネタばらしのようなところがあって、あまり好きではありません。本人が書くならいいでしょうが、傍らで見ていた人が書くのはどうか。
辻邦生は意外と子どもっぽかったことが分かったことは驚きですが、また芸術文学領域であれば、なんにでも関心を寄せるようなところがあり、また追求の度合いが激しかったことも分かりました。その分野のプロとして完璧でないといけないという使命感、たくましさが感じられます。が、一面それは人間としては窮屈なものでグロテスクな印象もあります。近代システムというもののなせる業なのかもしれません。
「打出の小槌」と呼んでいた小説技巧の種帳を作って、それを参照していたことが書かれていましたが、その種帳がどんなものか見てみたいし、文中で紹介されていた辻邦生の作品―幻想短編集『黄昏の古都物語』、世紀末の五つの都市を舞台として、不吉な運命を秘めた宝石や、大理石像や砂時計を媒介として、奇怪な事件が次々と起こる『夜ひらく』、奇想天外なサーカス一座の空想・冒険小説『天使の鼓笛隊』はぜひ読んでみたい。