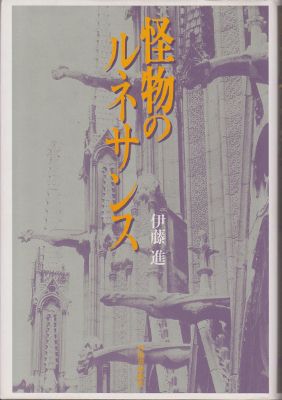この本は、主として中世から16世紀頃までのヨーロッパで報告されている怪物について書かれています。もともと著者は16世紀フランス文学が専門のようですが、パリの裁判所員だった人の日記を読んで、驚異や奇蹟がたくさん出てくることから、他の文献も渉猟するうちに、怪物のオンパレードに気づき、怪物にはまったということです。大きく二つに分けられ、ひとつは旅行記や博物誌、動物寓意譚などに登場する異境の動物や人間、もうひとつは市民の日記や瓦版で噂されているヨーロッパで生まれた畸形について書かれています。
前者についてはこれまでの読書でも数多く取り上げられていたので、そんなに驚きませんでしたが、衝撃を受けたのは後者、この時代のヨーロッパに続々と畸形の新生児が誕生したということです。私なりに考えると、ひとつの理由はこの本の例でも見られるように、プロテスタントが腐敗した旧教を非難するために話を捏造した、もうひとつは、病気か何かの流行によってこの時期そういう現象が実際に起こった、もうひとつはたんなる勘繰りですが、実はいまでもこの程度の確率で世界中で畸形が生れているが、生まれてもすぐ闇に葬っているので分からない、ということではないでしょうか。
それにしても畸形のオンパレードは食傷気味。とくにシャム双生児について豊富な事例が紹介されていますが、いろんなパターンのなかで、おでこだけが癒着した姉妹の例は悲惨としか言いようがありません。一方が前進すれば他方は後ずさりしなければならず、まっすぐ前を見ることができないので常に横目で見たということで、10歳まで生きたそうです。
異境の動物や人間のなかで、珍妙だったのは、くるまって寝るに充分なくらい大きい耳朶をもつ人々(p56)、視線をとおしてどんな病気も吸い取り、天空に病を運んで燃やしてしまう―真っ白な幻鳥カラドリウス(p76)、火に炙っても焼けないで、冷たい泉水でこんがり焼きあがる魚(p90)。図にも面白いのがありましたので、いくつかご紹介しておきます。
 マンティコラ
マンティコラ 鶴首人
鶴首人
 ブレムミュアエ
ブレムミュアエ
この本のなかで興味を惹いたのは、自然と怪物の関係についての議論で、「神々が未来を予知できないことはないので、未来について何らかの徴を示すはず」とするキケロの延長線上で、「怪物はその姿・恰好でもってその災厄のなんたるかを意味する」と主張するイシドルスがいて、自然から逸脱した怪物を人間への警告とする意見がある一方、「畸形は通俗的には自然を逸脱したものと見做されるが、物の自然な秩序の埒外にあるわけではない。単に自然の悪戯であって、なんら恐れるに足らない」と言うアリストテレス、「神が全体の美を見渡して諸部分を配置したのだから、怪物が社会的混乱や無秩序を意味することはない」と考えるアウグスティヌス、さらには「何が異常で、何が正常か。己の無智をも省みずにそれらを峻別しようとするのは、人間の傲岸以外のなにものでもない。どんなものでも自然に従わないものはない。われわれの理性が達することのできない事柄を、怪物とか奇蹟とか呼ぶだけ」というモンテーニュの意見がありました。両者とも神が意志をもって自然を創造したという点に立っているのが西洋らしいところです。
結局すべては自然に含まれるもので、反自然と思われるものは、ひとつは習慣や日常から逸脱した珍しいものであったり、人間が内燃機関を発見して以降、世界を大きく作り変える人工の力を得たために、それまでの自然観と齟齬が生じているということに過ぎないのではないでしょうか。そういう意味では現代の都会的環境やコンピュータ社会も自然なわけです。そしてもしそれが行き過ぎて人間が滅んでしまったとしてもそれは自然です。
もうひとつ面白かったのは、存在はすべてつながっていて、極端から極端へと移行することはなく、必ず中間のものを介しているという考え方で、ジャン・ボダンの次の言葉に現れています。「石と土との間には粘土と洞窟がある・・・石と植物の間には、根や枝や実を生じる石化植物たる珊瑚の種類がある・・・陸棲動物と水棲動物の間には、ビーバー、カワウソ、亀、河川に棲息する蟹のような両棲動物がある・・・他の獣と人間の間には猿や尾長猿がある。あらゆる野生動物と叡智的な自然の間に、神は肉体のような滅びる部分と叡智のような不滅の部分をあわせもつ人間を置かれた」。人間と猿との間に野人がいることで存在の連続性が保たれると言います。
16世紀は予言の世紀で、1520年から10年間で、占星術をベースにした予言関係の小冊子は133冊もあり、著者は56名にものぼると書かれていました。そう言えばノストラダムスの予言も1555年でした。
著者は最後に、16世紀末以降の怪物観の変遷を次のように書いています。知識人たちは次第に怪物趣味に背を向け、17世紀に入ると、デカルトの機械論的哲学の影響もあって、怪物は合理主義的な思考によって信仰の領域から除外され、畸形学(テラトロジー)という医学の領野に組み込まれて生理学的、発生学的な分析を施されていく。怪物はもはや恐怖と不安の形象でなくなり、一部の蒐集家たちの珍品陳列室を飾ることになる一方、見世物として一般大衆の好奇と娯楽に供されていく。驚異は好奇に取って代わられるのである。このとき怪物は脱魔化され、16世紀におけるようなインパクトを与える魔力を失っていく・・・。
現代人は魔物を安心なものとして楽しんでいるという、前に読んだ『河童の研究』と同じ指摘で、著者は、「400年前の人々と現代の私たちと、いったいどちらが真摯な生き方をしてるのだろう」と憤懣を込めた結語を書いています。近代以前の人間は真剣に魔物と対峙していたという主張ですが、現代人も同じく真摯に生きているのは同じで、ただその対象が魔物からいわゆる科学に移っただけなのではないでしょうか。
かなり分厚い本ですが、多くの事例をしかもひとつずつ丁寧に紹介していること、叙述の重複が多いこと、引用文が長いことが理由でしょう。第三章は第二章を別の形で報告したものともいえるので、編集上の工夫が必要だったと思います。