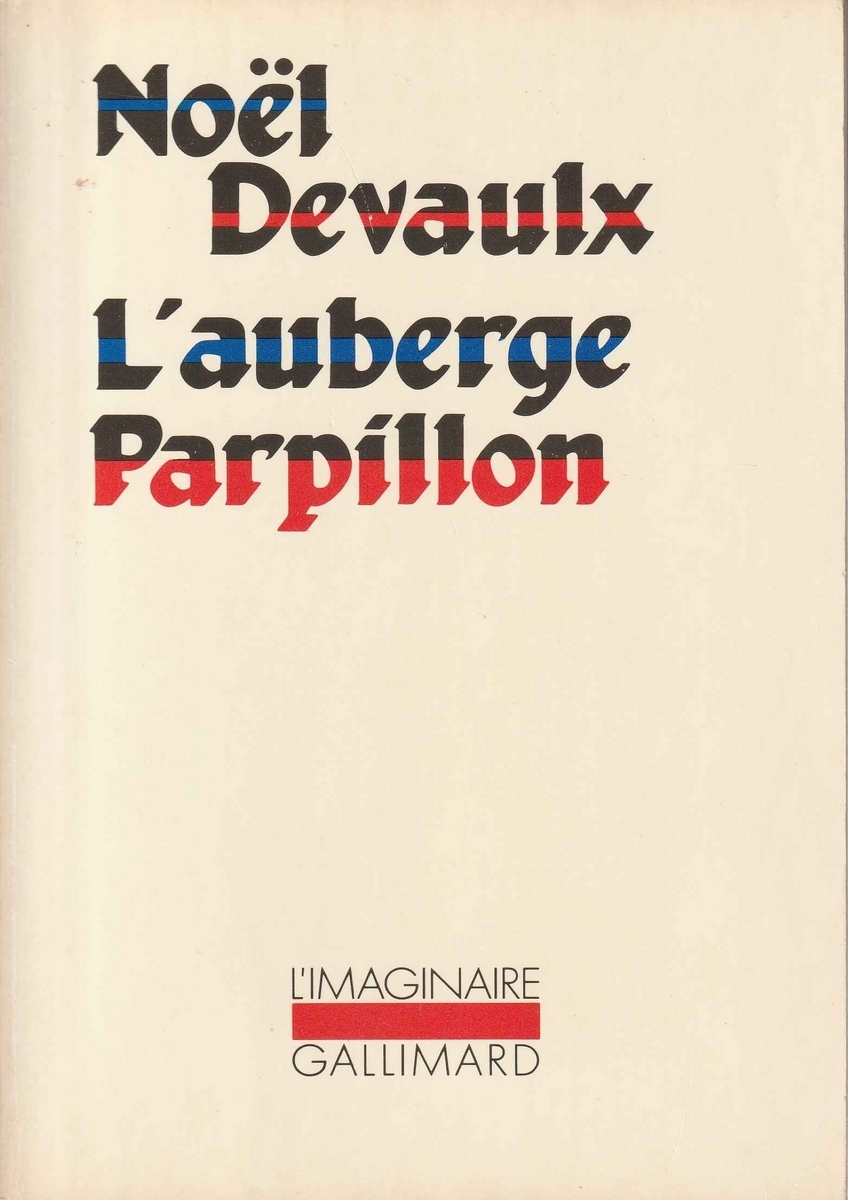
Noël Devaulx『L’auberge Parpillon』(GALLIMARD 1984年)
昨年読んだ『LA DAME DE MURCIE(ムルシアの貴婦人)』がものすごかったので(2022年4月5日記事参照)、シュネデールの『フランス幻想文学史』でも第一小説集でありかつ代表作として紹介されていた本書を読んでみました。昨年も書いたことですが、筆致の謎めいた雰囲気は最高。露骨な怪異が存在しないなかで、疑念を抱かせるような束の間の印象があり、それが現実の中に徐々に浸蝕して、幻想を広げていくといった筆法です。
文章が難しいのも同様で、途中で投げ出したくなるような部分もありました。それでも、その難解さを魅力のひとつとして、分かる部分を繋ぎ合わせながら何とか読み進めることができました。たぶん3割方は間違って解釈していることでしょう。難解さは作品によって異なり、いちばん難渋したのは、「Le Gâteau des Tailleurs(テーラー祭の供物菓子)」で、何のことかさっぱり。比較的読みやすかったのは「En marge du cadastre(土地台帳の余白)」で、気安く読めました。もちろん一つの作品の中でも、何度読んでも意味不明な部分もあれば、比較的読みやすい部分もあります。
小説の場合、普通は、解説とかあとがきの方が論評調で難しいことが多いですが、この本では、ジャン・ポーランのあとがきの方が読みやすい。しかも、面白いことに、ポーラン自身が、この小説集の美質として、読みにくさを告白していることです。「本を地面に叩きつけねばならなくなる」とも書いていました。ポーランによれば、それが美質なのは、速く読める本にはろくなものがなく、その分早く忘れ去ってしまうものだから、というのが理由で、何度も壁にぶち当たり、作品の意図を理解し同意するまでにいかに困難があるかということが、作品にとって重要とも書いています。
1937年から1944年までの間に書かれた7つの短篇が収められており、初版は1945年刊。そういう先入観があるからか、作品の中に、第二次世界大戦の重苦しく荒涼とした雰囲気が漂っているような気がします。ポーランも、作品の中に、死とか、生きる意味を失ったまま生き続ける人々が描かれていると指摘していましたし、「Le vampire(吸血鬼)」について、「農場はフランスを表わし、老人はペタン将軍、吸血鬼はドイツ軍」を表わしているという見方があることを紹介していました。
細かいところで、いくつかの感想がありました。
作品のところどころで、話が横道に逸れて、延々と続いたあと、例えば、「喋りすぎたようだ。テーラー祭りに話を戻そう」(p55)といったような表現がありましたが、これも一種のフランス式饒舌体でしょうか。ただでさえ分かりにくいのに、読んでいるうちに迷路のようなところへ入りこんでしまい、元の話が何の話だったか忘れてしまいます。
「Le veilleur de nuit(夜警)」のなかで、「霊感が肉となる」(p67)、「言葉が肉となる」(p75)という似たような箴言が二つ出てきましたが、これは先日読んだ心脳理論の言う「心と肉体は一体」という考えにも通じるものがあるような気がします。
「L’auberge Parpillon」、「Le vampire」ともに、主人公が手芸材料店のセールスをしているという設定ですが、もしかして、ドゥヴォーの個人的な経験が関係しているのかも知れません。
恒例により各篇の紹介を下記に(ネタバレ注意)。私の思う最高作は、表題ともなっている「L’auberge Parpillon」、「Le vampire(吸血鬼)」の二作。次いで「Environs de l’absence(不在の周辺)」、「En marge du cadastre」でしょうか。
◎L’auberge Parpillon(パルピヨン館)
かつては賑わっていたが今は崩れかかったような館に宿を見つけることができた。部屋もじめっとして汚かったが埋め合わせるように、老女主人の料理がおいしい。手芸材料のセールスの合間に、近くの展望のいい広場でうたた寝をしていると、日傘をさした婦人が踊るようにやってきて挨拶し礼拝堂の鐘の音とともに消えた。その思い出が強烈だったので、その後何度か広場に上ったが会えなかった。ある夜、部屋から外を見ると、中庭に豪華な馬車が3台停まっていて、12人の女性が出発の準備をしており、その中にあの婦人もいた。ここは娼館で女主人はやり手婆だったのか。下に降りようとするも、馬車はすでに角に消えていた。
◎Environs de l’absence(不在の周辺)
ある日、女の子が突然やってきた。「どこへ行くの?」と聞くと「ここ」と言う。孤児だと思って、家政婦と一緒に世話し教育を施すが、勉強より家事に向いてそうだ。その子への愛を家政婦と競い合うようになったりもする。賢い子で、子どもらしい遊びもするが異様に敬虔な態度に驚かされる。聖体拝領を受けさせようと準備をしていたら、その前の日、来たときと同じようにかき消えていた。もしかして天使だったのかも知れない。「あとがき」で、ジャン・ポーランは「悪魔だったのかも知れない」と書いていた。
〇Le Gâteau des Tailleurs(テーラー祭の供物菓子)
ある港町の奇態な祭の話。人々は卵を装飾品として身につけ、菓子を供物として捧げる。そこには人肉嗜食の名残があった。聖なる遺体に死化粧を施すのはテーラーの役割だ。どうやらキリストと密接な関係のある祭らしい。夜になり人々が居なくなると亡霊が跋扈し、我々は不安におののくのだ。(難しすぎてよく分からなかった)。
〇Le veilleur de nuit(夜警)
湯治に精通した主人公がある町を訪れる。宗教が浸透している町で、修道院に泊ってそこの神父に私淑し、カテキズムを受けることにする。もう少しで受理というところで、町に微妙な変化が訪れた。最初は古びた建物が崩れただけだったが、次に地滑りが起こり、谷から水が溢れ出してきた。人々は逃げ惑い修道院に押し寄せてきた。カタストロフを前にして、神父も「神はもはや我々の知っている神ではない」と言う。しかし、主人公は水深の数字が刻々と増してくるのを聞きながら、ちょうど切りのいい数字になったとか、どこかとぼけているのだ。
◎Le vampire(吸血鬼)
手芸材料のセールスをしている男。中世の雰囲気を残すある町で、古びた櫓のある建物の中に入ってみると、中庭で、50人ぐらいの村人たちが何か儀式のようなものをしているのが見えた。村人らは何かが起こるのをひたすら待っているようだ。すると、地下から呻きに続いて叫びが聞こえて、人々は絶叫した。再び訪れた沈黙のなかで、地下室の天窓から下を覗くと、暗くてよく見えない中に、なにか蠢く白いものが見えた。
◎En marge du cadastre(土地台帳の余白)
妻と自動車でオプールという町を目指している。人狼の住むところだと忠告を受けるが構わず進む。途中で自動車が故障してしまい、日没の迫るなか徒歩で行くことにする。山を越えたときはすでに陽は沈んでいた。山を下りたところでランプを持った農夫と出会い、ここがオプールかと聞くと、笑うだけだった。この村の住人は中世のような厚地の服を着て、何か不自然さが漂う。教会に入ってみると100年も使われてない状態だった。夜、寝付かれず、村はずれまで行き、帰ろうとしたら教会の鐘が鳴った。それで魔法が解けたらしく、現代の町が姿を現わす。一種の桃源郷譚。
〇Les tribulations d’Antonin Suberbordes(アントナン・スュベルボルドの苦難)
友の苦難の歩みの告白を聞いている。理科系の学校を出て事業に真面目に取り組み順調だった男だが、出張で叔母の家に泊まったとき、顔がなくその代わり黄楊の木のつるんとした頭をした男を幻視してから、その男が四六時中まとわりつくようになり、すべてが台無しになってしまう。引越ししてしばらくは解放されたものの、真夜中に大家の娘が煉瓦を積んでそれを足台にして屋根裏部屋に消えるのを目撃し、真似しようとして落下してから、また黄楊頭の男を見るようになる。そこで田舎に引っ越しすることにしたが、今度は、ピグミーのような小さな種族の大軍が襲来して、町は焼かれ、本人も捕虜となったというのだ。二人が話していたのが精神病院の庭という落ちがついている。