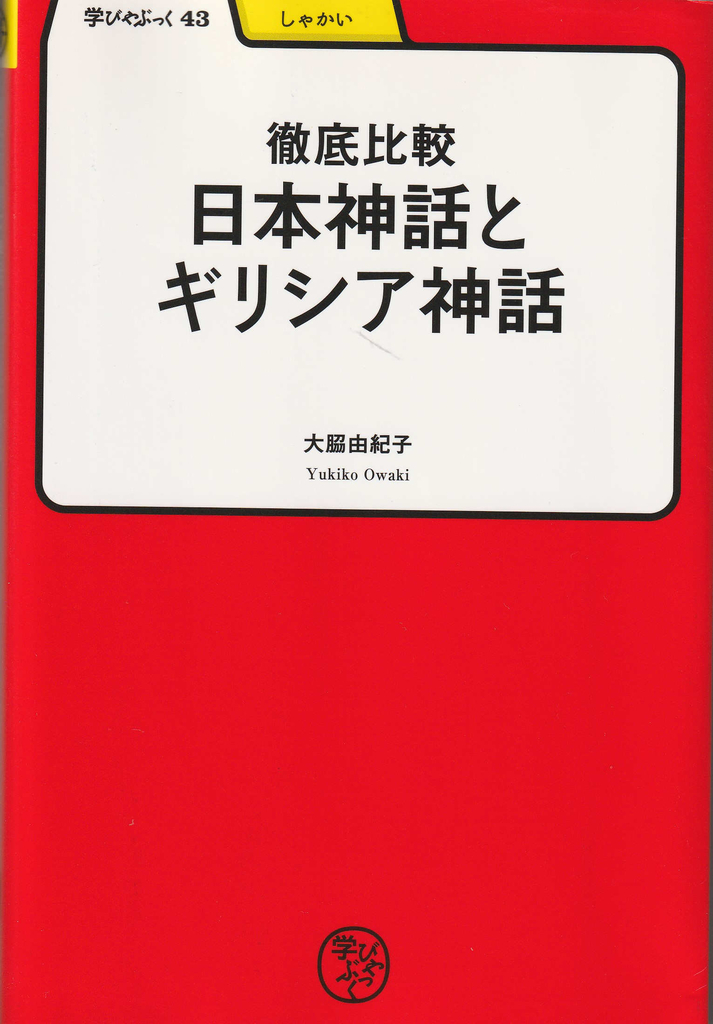吉田敦彦+山崎賞選考委員会『神話学の知と現代―第8回哲学奨励山崎賞授賞記念シンポジウム』(河出書房新社 1984年)
山崎賞というのは、哲学者の山崎正一が大学退職金の一部を基金として、哲学の研究で優れた業績を上げつつある人の将来の研究に期待する意味を込めて贈る賞で、村上陽一郎、市川浩、坂部恵らが受賞しています。この本は第8回目に受賞された吉田敦彦を中心に開かれたシンポジウムの記録です。2部に分かれていて、第1部はフランス文学者の渡辺守章、第2部は神話学者の大林太良をゲストに、活発な議論が展開されています。
シンポジウムや座談会の記録は、堅苦しい論文を読むのとは違って、言葉が平易で分かりやすいこと、質問と回答という形なので問題点が浮き彫りになること、本音トークが聞けること、楽しい雰囲気が味わえるなどありますが、この本はそのシンポジウムのよいところが出ています。山崎正一と吉田敦彦両氏があらかじめ構成をよく練られたもののようで、吉田敦彦の基調報告、ゲストのコメント、さらに哲学者の面々による質問という形で進行、座長の山崎正一氏が味のあるまとめをしています。
山崎正一の問題意識は明確で、この賞の過去の受賞者の顔ぶれを見ても、近代科学の考え方あり方を乗り越えようとする視点が感じられますが、この本でも近代科学主義が欠落させている部分として神話を取りあげ、最後の結論部でも、神話は科学を補完するもので、人間はどうしても抽象的なのっぺらぼうな世界に生きることはできず、文化という一種の澱みみたいなものと切り離しては生きられないと主張されているように受け取りました。
いくつかの興味深い論点が見られましたので、いつものように曲解をまじえて紹介してみます。
①現代の神話:現代の人間はそれぞれが別の価値で動いているように見え、自分たちも意識していないが、実は深いところで共通する神話を生きているのでは(吉田、p40、243、256)。これに対し、目に見える形でストーリーになっていないと神話とは言えないのでは(大林)という意見があり、神話の原材料みたいなものと訂正している(p258)。→これはユング的な心理学の領域にも関係してくるものだと思う。
②神話の読み直し:ヨーロッパ人にとって神話のような機能をしているものは、日本人にとっては「日本の神話」ではないかもしれない。例えば自然観や、伝統詩歌によって伝承され共有されている感覚的な風景のほうがそういう機能を果たしているのでは(渡辺、p45)。神話には言説、図像、儀礼の三つの要素があり、ギリシア神話には儀礼が残っていないが言説は多く、日本神話はその逆で(渡辺、p82、137)、もし神道の儀礼がなくなってしまえば、日本神話は残らないだろう(渡辺、p142)。
③神話の定義:例えばキリスト教の信者からは神話という言葉は絶対に出ないことからすると、神話というのは自分たちの信じていない異教の神々の話という前提がある(渡辺、p36)。神話の言葉というのはもともと音声言語で、身振りとかを全部含めた言葉の呪力が神話を支え、神話が土着的に生きていたが、今はそれが普遍化され神話の言説だけが知識として瀰漫している。それは真の神話ではない(渡辺、p52)
④古代神話のルーツ:インド・ヨーロッパ語族の神話の三機能構造がアメリカ大陸で見られることについて、インドから東南アジアを通って、さらに太平洋をこえたという経路があり得る(大林、p185)。日本については、農耕起源神話など縄文中期の文化はニューギニアなどの古栽培民の文化と近似していただけでなく、オセアニアを経由してアメリカ大陸の古栽培民の文化とも、近似性を持っていたのでは(吉田、p214)。弥生時代から古墳時代の前期までは日本の文化は中国南部の文化と連なっていたが、古墳時代の半ばごろから北の騎馬民族文化が入ってきた(江上波夫の説を紹介、大林、p186)。
⑤親離れ:現代の日本にはいつまでもスサノヲ・コンプレックス(母からの分離の拒否)から脱却できない男たちが満ち溢れている。ある男には妻が、べつの男には娘が、また別の男にはマイホームが、母の代りとなっている(吉田、p241)。もともと動物の場合は生まれた時点で母親しかいない場合があり、父親という存在は人間になってからかもしれないし(山崎、p241)、オスとメスがコドモを育てることに協力する動物でも、コドモが一人前になる前に子と別れるので、動物の場合は父親の意識も母親の意識もない(吉田、p241)。
⑥人間と動物:人間がなぜ知恵を働かせ、整合性を持った神話や文化を生み出して生きるのかと言えば、人間が自然的には整合性を欠いているからで、人間以外の生物は本能に従って生きるだけで、種の存続のためにもっとも合理的で整合的な環境に適応した生き方ができるので、サピエンスである必要がそもそもない(吉田、p260)。人間は秩序のために無秩序を、合理のために非合理を、根本的に必要としている。同種の動物同士がむやみに殺し合ったり、雄が雌を強姦することはなく、人間の専売特許(吉田、p261)。
私なりの面白い発見としては、
①タイラーやフレーザーあるいはデュルケームのような大学者たちは、だれも実際に未開人の所に行って研究することは一切せず、宣教師、行政官、探検家、商人などの報告を資料として分析していた(吉田、p17)。→これはアームチェア・ディテクティヴのようなものか。
②お釈迦さまも、豚肉食べて豚肉の中毒で死んじゃいました(大林、p218)。→自ら禁を犯したのかと調べてみると、釈迦の時代は肉食可だったみたい。
③むかしは若者宿、娘宿というのがあって、若者宿の方から集団的にデートに押しかける時、いちばん下のやつが提灯を持って先に行く。そこから「提灯持ち」という言葉ができた(大林、p248)。
④欧米化に対して自国文化の伝統のアイデンティティが言われるが、実を言えば、アイデンティティなんかどうでもよく「抵抗したい」ということ。金持ちになったら家系図も欲しいという場合、なぜ欲しいかといえば、こちらももともと立派なものであったと言いたいということ(山崎、p272)。