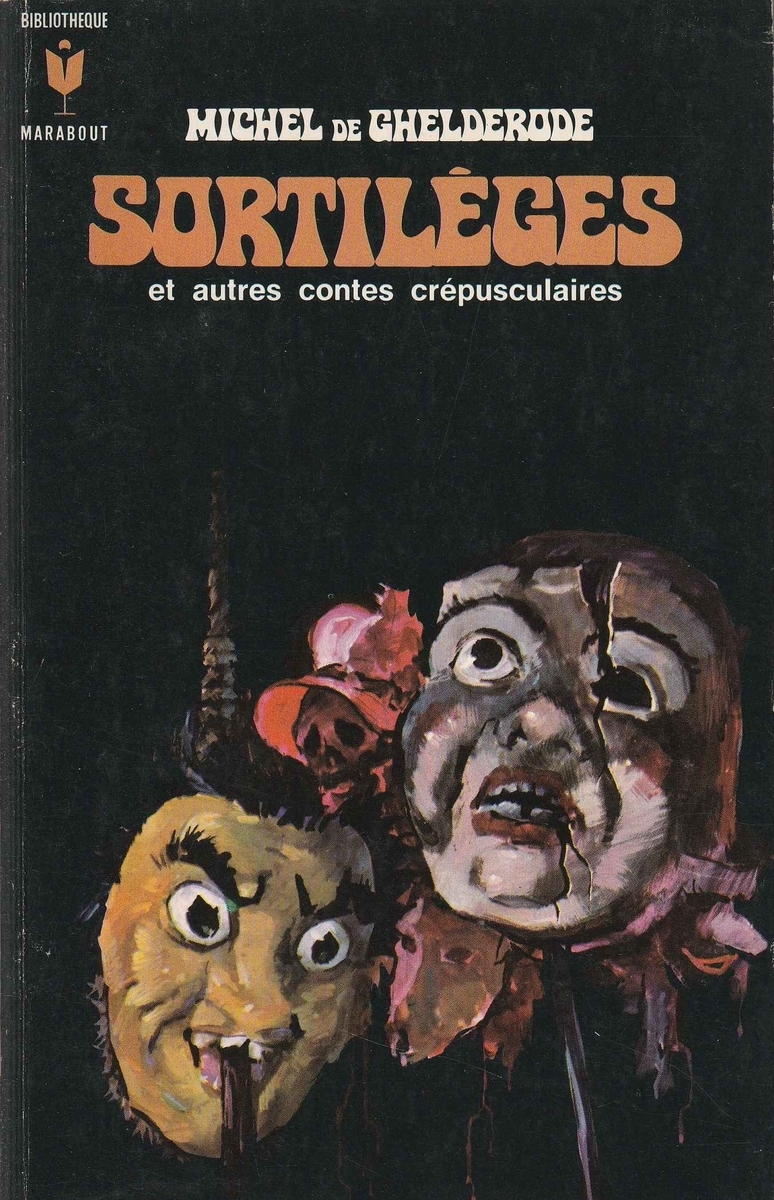JEAN-PIERRE BOURS『celui qui pourrissait』(marabout 1977年)
5年ほど前、パリの幻想小説・SF専門古書店「L’amour du NOIR」で大量買いした中の一冊。あまり聞いたことのない作家ですが、1977年のジャン・レイ賞を受賞した人で、本業は弁護士のようです。バロニアンの『panorama de la littérature fantastique de langue française(フランス幻想文学展望)』には、この本ともう一冊切り裂きジャックを題材にした長編ミステリーが紹介されていました。他にも何作かあるようです。
話の運びにも表現にも卓抜な技が感じられます。ただいくつかの作品では、解剖学的なグロテスクな描写が多すぎて気持ちが悪いのが私にとっては汚点。これがなければもっと評価が上がるのにと思いますが、逆になければ作品として成立しなくなるかもしれません。難しいところです。身体の組織に詳しいのは医者になろうとしていたからでしょうか。弁護士の緻密さに対する感性と関連があるのかも知れませんが、細部へのこだわりが凄く、一種の極レアリズムを通しての幻想と言えるのかもしれません。どこかロブ=グリエや岩成達也の細部の客観描写による幻想性に通じる感じもしますが、少し違うようにも思います。
もう一つの特徴は、バロニアンも書いていましたが、自己同一性の揺らぎをテーマにしたものが多いことです。ドッペルゲンガーを見る「Aujourd’hui l’abîme(今日は奈落へ)」、病気で自己が崩壊していく「Celui qui pourrissait」、人格が入れ替わる「Procédure contradictoire(真逆になった裁判)」、自分の妄想が殺人者を造り出す「La vérité sur la mort d’Aaron Goldstein(アーロン・ゴールドスタインの死の真相)」、厳格な裁判長と慈愛に満ちた人格に引き裂かれる「La mort du juste(正義の人の死)」。
10の短篇が収められています。なかでは「Procédure contradictoire」、「La vérité sur la mort d’Aaron Goldstein」が秀逸。残酷味が目に余るのが難点ですが、「Celui qui pourrissait」、「Le peuple nu(剥がれた人々)」、「Entre Charybde et Scylla(窮地と死線のあいだ)」もそれ以上に力のある作品です。次に続くのが「Histoire d’A(A嬢の物語)」、「Le château des réminiscences(思い出の城)」、「Aujourd’hui l’abîme」といったところでしょうか。
簡単に内容を紹介しておきます(ネタバレ注意)。
〇Celui qui pourrissait
有能な産科医として将来を嘱望され、婚約もしていた青年に、皮膚病の嵐が襲いかかる。湿疹、ヘルペス、天疱瘡、丹毒、梅毒、天然痘、癩病と、ひと段落ごとに新たな病気が加わって身体が崩れていく語りの恐ろしさが物語の迫真部分。皮膚病に関する専門用語が頻出し、克明な描写が続いて気持ち悪いこと限りなし。
◎Procédure contradictoire
亡き父が懇意にしていた裁判長が新しいポストに就くお祝いの会に出た。父からは気難しい陰気な性格と聞いていたのに、まるで反対の陽気な浮かれた男だった。同席した友人に訳を聞くと、自分の解釈だがと驚くべき話をした。裁判のあいだ、罪人が被告席から裁判長に念を送り続けて、死刑を宣言した直後に魂を入れ替えたというのだ。処刑されたのは裁判長で、今居るのは罪人だと。
〇Histoire d’A
『Histoire d’O(O嬢の物語)』を意識したと思われる作品。秘密宗教の淫猥な密儀で、教徒たちによって、若い娘らが被虐の奴隷のようになっている。教義の掟は厳しく、開かずの扉があり、その中にばらばらの手足を見たという噂があった。主人公は一人の娘に恋に落ちるが、ある疑念が湧き上がってきた(ネタバレ強烈のため省略)。淡々とした語り口が結末の意外性を盛り上げている。
〇Le peuple nu
叔父の影響で解剖に興味を持ち法医学者になった主人公が、引退した叔父の館での引っ越し祝いの仮面舞踏会を手伝うことになった。きらびやかな衣装と仮面に身を包んだ参会者と語らいダンスをし、オフェーリアの仮装をした女性と恋に陥るが、手袋を取ると…。これまで解剖して来た屍体が憎悪の叫びを上げながら迫って来る場面はゾンビ映画を思わせる。
Divin marquis !(聖侯爵!)
ある純真な女性が、交霊術で、誰の魂を呼び出してほしいか聞かれ、どんな人かよく知らないが文学サークルで話題になっていたサド侯爵と答えた。侯爵は死後地獄に落ち、無心の心から呼ばれたときにのみ現世に戻れるという刑罰を受けて、氷山に閉じ込められていた。二人の会話のすれ違いが面白い。
〇Le château des réminiscences
嵐の夜に馬で出かけては村人に悪さをする少年。ある夜はじめて入った森のなかで、沼の対岸に城を見つける。それからは毎夜何とか城へ辿り着こうとして叶わない。ある冬の夜、森の空地で見つけた黒装束の騎士の後をつけると沼の浅瀬を伝って城へ入ることができた。そこには広い競技場があり中世そのままの馬上槍試合が展開されていた。束の間の幻影を見た少年の思い出。
◎La vérité sur la mort d’Aaron Goldstein
ある富豪の実業家を殺したいと恨んでいる男のもとに、奇術師が現われ、トランプマジックを見せ、男の素性と思いを的中させる。殺したい人に会わせてやると男を案内し、眼の前で実業家を切り殺す。すると奇術師の姿は鏡に映らなくなり、警備がやって来たときは、姿も消えていた。怨念が奇術師の姿で現われたのだった。単純な話だが、語りの面白さが魅力を十倍に引き立てている。
La mort du juste
中世の異端審問官のように狂信的な裁判長。弁論も鮮やかに、軽犯罪人に極刑の判決を連発していた。だが私生活では慈悲深い善行の人で、1カ月だけ孤児を預かる。その子は天使のように可愛く無邪気で質問を連発し、裁判長の様子はだんだんとおかしくなって行った。子どもが帰る前の夜、裁判長は子どものベッドの前で自殺していたが、天使のような子もベッドから消えていた。
〇Entre Charybde et Scylla
喉の手術を受けることになった神経質な主人公。医者は大したことはないというが、心配で本を読んだり音楽を聴いたりして気を紛らわせる。医学書で手術の仕方を読むとますます不安が募って来た。手術の前の晩、眠れないのでドライヴするが…。車の走りと手術の妄想が交互に描かれ、クレッシェンドの高まりとともに最後に一点に収束して終わる。
〇Aujourd’hui l’abîme
厳格な宗教教育を受けて育ったが、子どものころ娼婦街を車で通ったときの思い出がこびりついて、大学に入った途端、放蕩生活に陥り一人の娼婦のもとに通うようになる。学校にも行かず全財産を注ぎ込み、飲まず食わずで痩せ細るうちに、その娼婦の家で自分とそっくりの男とすれ違う。彼女は魔界の女当主で、若者らを次々に同じような亡霊と化してこの世から葬っていたのだ。