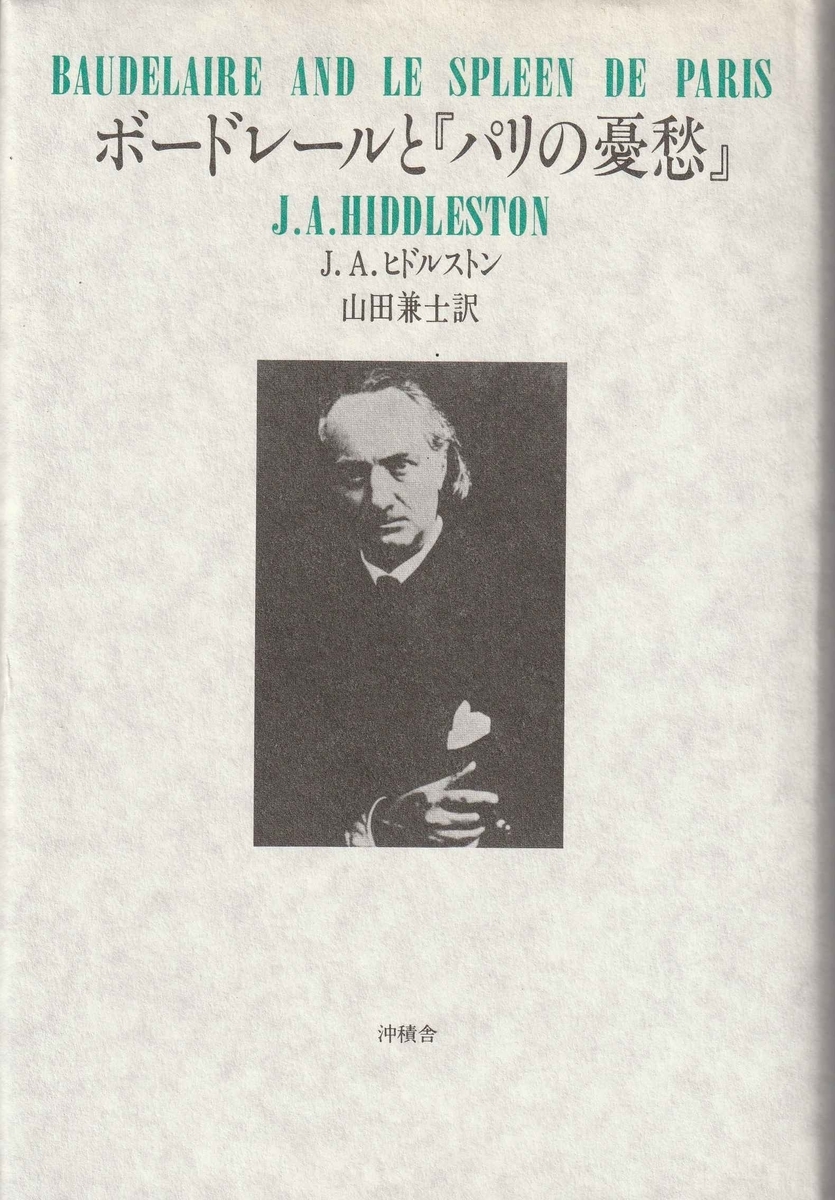川島昭夫『植物園の世紀―イギリス帝国の植物政策』(共和国 2020年)
川島昭夫『植物と市民の文化』(山川出版社 1999年)
ともに私の古本の師であり友人であった川島昭夫さんの本。『植物園の世紀』は遺著ですが、収められた論稿を実際に執筆した時期は1989年から96年で、『植物と市民の文化』よりも早く書かれています。『植物園の世紀』は大英帝国の植民地での植物政策を中心に、『植物と市民の文化』はイギリス国内の植物愛好趣味についてとりあげたもので、編者の志村真幸氏も書かれているように(p234)、双方は補完しあう関係にあります。
両著を通読してみて、ぼんやりと抱いた印象は、やはり川島さんらしさが随所に現れているということです。川島さんについては、大学時代にしか深いお付き合いはありませんでしたが、ひとつは彼の人に対する思いがとても強いということ。戦前・戦後間もなくの歌謡曲を諳んじ、山手樹一郎の時代小説を愛読するなど庶民感覚を大事にし、「関の弥太っぺ」などの人情噺に心を震わせると同時に、学生運動の余波からか、権力や権威を振りかざす者たちを嫌悪していました。科学に対しても高度な洗練された科学よりは、錬金術のような前科学、変人が編み出すような科学を愛していました。また美しいものに対する繊細な感性があって、言語感覚では塚本邦雄や日夏耿之介を好み、造形感覚では澁澤龍彦を偏愛していて、彼の下宿「海の星寮」には澁澤の書斎張りの奇怪なオブジェがあちこちにあったことを思い出します。
らしさが現れているのは、例えば、『植物園の世紀』で、大きな視野からこの時代の帝国の動きを経済的、地勢的に分析する一方、植物園運営者やプラント・ハンターの人物に焦点を当て物語る姿勢です。「一攫千金をはたして、本国へ帰る。それが在地のプランターたちの行動様式であった。植物の悠々たる楽しみは、ヒントン・イーストのごとき、土着化したイギリス人、いわゆるクレオールの家系の出身で、ジャマイカを墓場にする覚悟のあった人にだけ可能であったのかも知れない」(p131)や、「キッドは、ベンガルに植物を集めることで、会社領土のいたずらな膨張が不要になると考えたが、イギリスによるインド支配はさらに拡大をつづけたのである」(p156)という文章には、ヒントン・イーストやロバート・キッド大佐に対する熱いシンパシーが溢れています。
美に対する感受性は、何よりも文中に挿まれた川島さん好みの数々の図版が証明しています。この本の装幀も素晴らしく、古書収集家で愛書家であった川島さんもきっと喜んでいることでしょう。また「ミルラ(没薬)、オポナクス(樹脂)、オポバルサム(樹脂)、ガム・トラガント、ガジュツ(白鬱金)」(p100)と、呪文のように香料を採る植物を列挙するあたりは塚本邦雄を思わせます。私がすぐこの本を読もうと思ったのは、遺著だったということもありますが、香料のもととなる異国の植物がたくさん出てくることで、このところ読み続けていたボードレールの世界と共通するものを発見したからです。他にも随所に、学術専門書の体裁を取りながら、詩人であり、ボルヘスであるスタイリッシュな文体が見え隠れしています(これは私の思い入れだけかもしれません)。
この二冊の本で指摘されていることで、無知な私の知り得たことを紹介しておきます。
①高分子化学の技術発展によって工業製品で代替されるようになる以前、植物資源はあらゆる生活の局面で欠くべからざるものであった。植物資源の国外依存による財貨の流出を防ぐために、あらゆる植物を帝国領土内に集めようとする植物帝国主義が誕生する。ある土地に固有の植物を、別の土地へ移植するための輸送法、栽培法、さらに加工法が植物園において研究され、多くの植物学者やプラント・ハンターが活躍した。
②ヨーロッパの植物園は、大学付属の薬用植物園に起源がある。その主な機能は、初期の航海者がもちかえった未知の植物を収集し、その栽培と薬用効果の実験を行なうものであった。一方それとは別に、植物学者、園芸家、薬種商らが私的に行なった楽しみのための植物コレクションの系譜があり、その二つの系譜が一つに統合されたのが、キューの王室庭園であった。
③世界周航をしたクックのタヒチ情報は、文明を知らない人々が労働の苦役から解放され、原初の至福の状態に生きる楽園の神話として流布することになる。その神話的果実パンノキをイギリスへもちかえるべくパンノキ遠征隊が結成されたが、それがバウンティ号だった。→「この遠征は、バウンティ号がタヒチを離れた直後に起こった乗組員の反乱によって失敗に終わる」(p75)と、さらりと書くこの冷ややかな筆致は何ともハードボイルド。
④モーリシャス島を舞台とする『ポールとヴィルジニー』には熱帯産植物の農園が描かれているが、著者のド・サン・ピエールはパリの王立植物園の園長でもあり、この島に3年間滞在したことがある。そのとき、ド・サン・ピエールは、後にフランス最初の植民地植物園のもととなる農園を知っていた。それを作ったのはピエール・ポワヴルと言ったらしい。→ポワヴルはおそらくpoivre(胡椒)だろうが何かの縁か?
⑤インドの東部のコロマンデル海岸はヨーロッパ諸国の海外進出のもくろみが錯綜する地域であった。オランダはマウスリパタムに拠り、イギリスはその南にマドラスを建設、フランスはポンディシェリ、デンマークはトランケバールと、それぞれの定住地を有していた。→ポンディシェリは昨年読んだMaurice Magre『Nuit de haschich et d’opium』(モーリス・マグル『ハシッシュと阿片の夜』)の舞台になっていた。
⑥各国の植物研究者たちは国を越えた連携を行なっており、科学者の国際的な「共同体」というものに属していたことが分かる。また彼らを駆り立てた原動力は、自然界の調和に創造主の無限の摂理をみいだしていたプロテスタンティズムであったり、産業革命で成功した実業家たちが多かった非国教徒のクェーカー(この部分は『植物と市民の文化』)であったりした。またスコットランド人も多かったが、エディンバラ大学の教授で植物園長だったジョン・ホープの教育もさることながら、イギリス本国のなかの一種の外国というスコットランドの位置も関係している。
―以上『植物園の世紀』より。
①ロンドン植物園は会員制というシステムで運営された。同じように、市民たちによる自発的な団体としての「園芸協会」の付属施設として、地方都市の植物園がハル、グラスゴウなど12カ所にできた。同じ時期に、出版界でも、先に費用負担を呼びかけてから印刷する予約出版というシステムができ、また書物の購入者たちが、本の購入資金を共同で拠出し、購入した書籍を共同で管理する一種の読書クラブが組織された。これは公共図書館の起源の一つとなったが、こうした時代背景には、公共的精神の誕生ということがあった。
②地方の貴族は、カントリー・ハウスのまわりを庭園とその外側の狩猟用林地で包囲することで、領地の農民たちのぶしつけな視線から遮断し、目に見えないことによってさらに威信を強化しようとした。さらに貴族同士でも、カントリー・ハウスを作ることで、威信をかけた社会的競争をはかった。イギリスにもともと自生する樹木はヒイラギ、イチイ、ツゲの三種しかなく、多彩な表情を求めたため、異国的な外来植物の庭園への大量配置という現象を引き起こした。
③園芸は、適度な身体の運動と、植物にかんする知的な興味とを結びつける「合理的な娯楽」の典型であり、しかももう一つのミドルクラス的な価値「家庭崇拝」ともよく合致した。労働者階級や農村の零細農民においても、花を守り育てることが流行し、ナデシコの栽培に熱狂するペズリのような工業都市もあった。が都市の過密により、労働者のあいだのフロリストの活動は消滅していき、郊外に居を移した中流階級の庭づくりに継承されていった。
④このヴィクトリア朝の園芸と植物への関心には、異国への憧憬と並んで、イギリスの農村への回帰願望がつきまとっていた。帝国主義下のイギリスで、イギリスらしさとは何かという問いに対して、短兵急に過去回帰的な田園風景をその答えとした感がある。「もしもイギリスらしさがあるとすれば、それは帝国とイングランド、都市と農村、進歩と回帰、二項対立的なさまざまな要素が、いずれが優位とはっきりした決着がつけられることなく共存し交じりあう妥協と折衷、エクレクティシズムであったとはいえないか」(p79)
―以上『植物と市民の文化』より。
もう少し彼とお話ができていたら、18、19世紀のオリエンタリスムとの関係や本草学との関係なども聞いてみたかったと思います。