
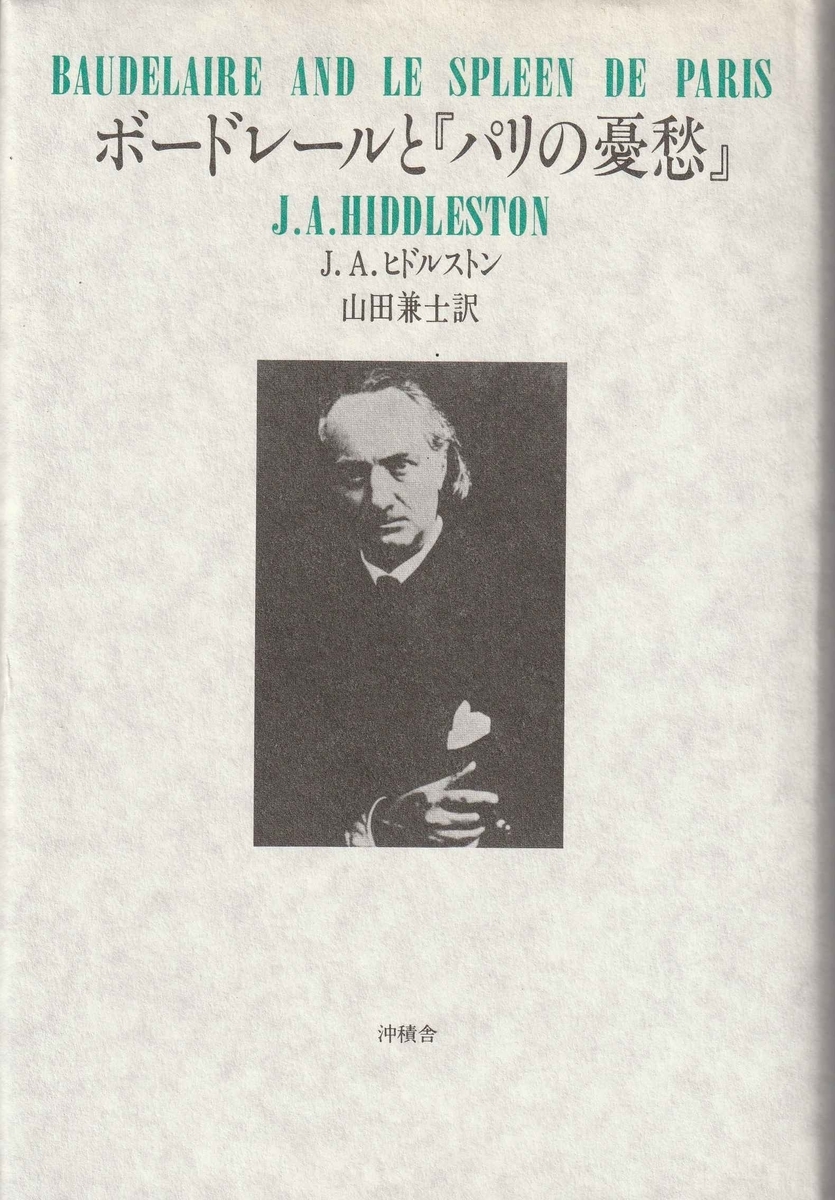
山田兼士『ボードレールの詩学』(砂子屋書房 2005年)
J・A・ヒドルストン山田兼士訳『ボードレールと「パリの憂愁」』(沖積舎 1991年)
これで、ボードレールについて書かれた単行本で私の所持しているものは最後です。今年1月から半年間ずっとボードレール関係を読んできました。まだ重要だと思われる阿部良雄や福永武彦、ジョルジュ・ブラン、マルセル・リュフなどが抜けていますし、雑誌がいくつかと、『悪の華』の翻訳書も残っていますが、ボードレールはしばらく間をおきたいと思います。読書は義務感が上回ってしまうと面白くなくなってきますので。
この二冊は著したにせよ翻訳したにせよ山田兼士が書いたもので、ともに文章中に括弧が頻出して目がちらちらしたのは困ったものです。とりわけヒドルストンの本は文人の発言や研究書への言及が多いのと、丁寧に訳そうとしていて文章が長くなっているのも原因だと思いますが、なかなか文章がすんなりと頭に入ってきませんでした。歳とともに集中力がなくなっているのが真相かもしれません。二冊で共通性が感じられたのは、『ボードレールの詩学』で、ヒドルストン本の中心テーマである『パリの憂愁』の話題が取り上げられているところです。
『ボードレールの詩学』は著者のボードレールについての三冊目の本ということで、前著からこぼれた雑多なテーマを寄せ集めたという印象がありました。三つの章からなり、第一章は、『悪の華』から『パリの憂愁』への移行を「夜のパリ」から「昼のパリ」への移行と見てその予兆を『悪の華』詩篇の中に探り、また『パリの憂愁』の前半部と後半部の女性像の差、ベルギーで書かれた『パリの憂愁』の最後の部分について論じ、第二章は、コローの絵画とボードレールの芸術論の接点について、第三章はコクトーの映画との共通性について考察しています。
恒例により、いくつか印象的だった論点を独断と偏見で要約し感想を交えて紹介します。
①『悪の華』から『パリの憂愁』へどういう変化があったかは、観照的態度から行動的態度へ、矛盾対立を統合しようとする照応の詩学から異化を際立たせる対位法の詩学へ、憂愁に満ちた深遠な夜のエネルギーから昼の日常的平俗性へ、と見ることができる。『悪の華』再版に入れられた「パリ情景」において、すでにその越境が試みられていた。→これは晩年のボードレールが直面した日常の悲惨を描くには昼のポエジーが必要になったということであろう。
②『パリの憂愁』に登場する女性像は、前半においては、「麗しのドロテ」に代表されるように、女神と生身の折衷的存在であり、大理石像や熱帯の風景とともに悦楽のイメージに彩られていたが、後半においては、「マドモワゼル・ビストゥリ」に代表される無垢な怪物としての不条理なイメージとなる。それは母オーピック夫人を祖型とする女性像であり、他の詩篇にもさまざまな年齢の姿で母が登場している。
③ボードレールが晩年に滞在したベルギーを罵った『哀れなベルギー』と同じ視点が、すでにボードレールの中学時代のリヨンでの手紙に見られる。→ボードレールは性格的に今いる場所に不満を持つタイプだったのではないだろうか。それが「anywhere out of the world」という言葉に表れているのでは。そしてリヨンの中学時代すでに革命にシンパシーを持ち社会的な意識に目覚めていたことが分かった。
④ボードレールの詩には、風景と人体とのアナロジーをベースにしたものがあるが、美術論においても、風景画の構造を人体の構造になぞらえるという観点を導入していた。コローの肖像画にはその応用が見られる。
ヒドルストンの本も三章からなり、第一章は、『パリの憂愁』が『悪の華』と異なり、詩集全体の構成を考慮していないことを述べた後、ほとんどの作品が芸術や芸術家をテーマとしていること、第二章では、ボードレールが良き感情の文学を嫌い、紋切型を装いながら、アフォリズム的表現を使って、読者を不快なモラルに導こうとしていることを具体的作品で検証し、第三章では、韻文と散文の違いを技法的な視点から解説し、日記や後期作品も参照しながら、『パリの憂愁』と『悪の華』の違いについて考察しています。
おぼろげにいくつか理解できたことを私なりに書いてみますと、
①『パリの憂愁』において、芸術家は、ロマン派の詩人たちが主張していた特権と栄光をほとんど失った姿として描かれている。道化としての詩人への言及は、『悪の華』では比較的少なく軽微なものだったが、『パリの憂愁』ではより発展し、主題の上ではるかに重要になっている。
②ボードレールは生涯の後半、韻文から散文への移行の技巧的な工夫に没頭していた。韻文のアレクサンドランを破壊して散文のリズムに置き換えたり、隠喩など比喩表現を縮小し、代わりに細部を拡大するなどした。語り、解説という知性的なものを優位に置き、アイロニックな不調和を侵入させることで、多様な調子を生み出した。その結果、韻文において実現していた抒情性は拒否され、不協和音の方へ重点が移行していった。→ボードレールは詩から逃れようとしていたとも考えられる。
③「老婆の絶望」の各段落の冒頭に「Etそこで」、「Maisところが」、「Alorsすると」という接続詞を置き、構造が際立つようにしているが、この技巧はベルトランに負っているものの、散文詩全体としてはベルトランの静的な世界とは無縁で、むしろ短さを志向したポーの短篇から得たものが多い。ボードレールはこのジャンルにおいていかなる真の先駆者も持たず、またいかなる適切な後継者も持っていない。→この後継者として、優雅な厭世観に満ちた瞑想的散文を制作したラブ、ルフェーヴル=ドゥーミエという紹介があったので、一度読んでみたい。
④ボードレールが『パリの憂愁』で成功させた美学は、現実界と想像界を混合し、生の深遠を不安定に露呈させる幻覚作用である。その技巧には、雰囲気や感覚を一瞬のうちに変化させる言葉、「しかしmais」、「ともかくtoutefois」、「突然tout à coup」の多様、また矛盾を生じさせ不安定や不調和の感覚をもたらす撞着語法がある。ボードレールが多くの散文詩で達成しようとしたものは、一種の不調和の詩であったように思われる。
なぜボードレールが韻文詩を捨てて、あるいはもう書けなくなって、詩的散文に向かったのか、また『悪の華』のどろどろとした怨念、呪詛のようなものがすっきりとこそげ落ちて、明るい諧謔や詠嘆に変わって行ったのか、まだもやもやと謎が残ります。