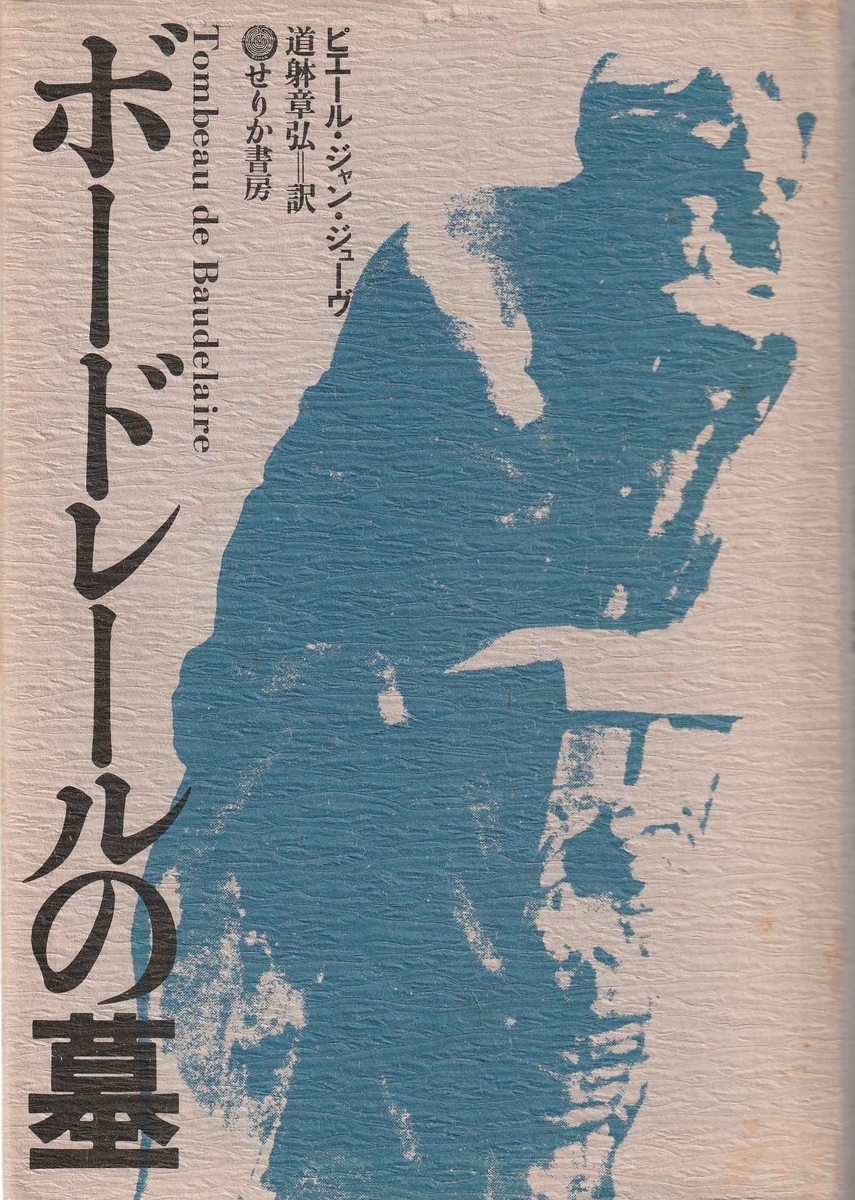矢野文夫/長谷川玖一『ボオドレエル研究』(叢文閣 1934年)
ボードレールについての本を続けて読んでいますが、いよいよ日本人の著作に移ります。時代的に古いと思われるものから。巻末に「ボオドレエル書誌」があり、それを見ると、ボードレールについての紹介ないし研究では、厨川白村が『近代文學十講』所収の「耽美派と近代詩人」で取り上げたのが最初のようです(明治45年)。大正から昭和初期にかけて、外国評論の翻訳などを含め、いくつかの論考が出ていますが、ボードレールに特化した単行本としては、次回取り上げる予定の辰野隆『ボオドレエル研究序説』(初出昭和5年)とこの本(昭和9年)が早いようです。
この本は4年前の京都勧業館古本市で買った本。200円という安さで、レジの人がびっくりしていたのを覚えています。この本の装幀は、福澤一郎という日本のシュルレアリスム絵画の草分けの一人。紙の手触りもよくどっしりした本です。
矢野文夫は、「悪の華」を日本で最初に全訳した人で、自ら『鴉片の夜』というボードレールの影響明らかな題名の詩集を発行し、美術評論などもしたとのことですが、一般にはあまり知られていないと思います。フランス文学者ではなく、語学力が未熟と本人は謙遜していても、なかなかどうしてフランスの原資料にもかなり目を通していて、当時としては画期的な業績ではなかったかと思います。長谷川玖一のことは私はまったく知りませんでした。『矢野文夫芸術論集』によると、慶応義塾の学生でフランス語専門の古本屋をしていて、矢野文夫よりも語学力があったので、分からないところを相談していたと言います。
この本は、ヴァレリー、ジッドの論文翻訳、アポリネールとバレスの論文紹介に始まり、思想全般、作品論、特定テーマ(ダンディスム、批評家としてのボードレール、若き日の詩集、病理学的研究)についての論考、伝記という構成で、全体に目配りのできたものとなっています。ただ作品論の一部はジャン・ロワイエル、若き日の詩集についての章はジュール・ムゲ、伝記はウジェーヌ・クレペの研究を紹介したものであり、他の本文中にもフランス文献の引用が多く、海外の研究を翻訳紹介したという位置づけになると思います。戦前の書物によくある絶叫型の主観的な文章がところどころ見られるのは愛嬌と言えましょう。
いちばん印象深かったのは、ジュール・ムゲの説を紹介した部分で、今まで読んだ本に書かれていたかもしれませんが、初めて聞いたような気がしました。それは、ボードレールのボヘミアン時代に、友人ら3人、ル・ヴァヴァスールとブラーロン、オーグスト・ドゾンと一緒に、詩集を出すことにしていたのに、寸前になってボオドレエルが抜け出たというものです。ムゲは、ブラーロンの筆名で書かれた詩の大部分はボードレールのものではないかと推理しています。ボードレールが初めてゴーチェのもとを訪れたとき、友人の詩集を贈呈したことがボードレールの「ゴーチェ論」に書かれていましたが、その詩集は上記の詩集だったとしています。たしかにわざわざ会いに行って友人の詩集を渡すというのは不自然な話です。
他に啓発的だったのは、これまで読んできた本と重なる部分があるかもしれませんが、詩の技法については、
①ボードレールの新奇さは「語彙の象徴主義」のなかにあり、比喩の絶えざる使用が特徴で、精神的なものと物質的なものの二面を融合するために、比喩を用いて交錯させた。とくによく使った対照法(antithèse)は、言葉の上の外面的なものではなく、心のうちの葛藤から生じた内面的なものであると指摘。「苦悩は喜悦の情と入り混じり、信頼の念は疑惑と交錯し、快活と憂愁とはうち混じり、そして彼は、怯々と、恐怖のさ中に、愛欲の本質を探らんとする」(p34)
②ボードレールが若き日に船に乗せられて行った異国の島の思い出が後の詩に反映していることに触れて、「半ばうすれて消え去った国の思い出が、詩人をあまりに細密な叙述から遠ざけている。そのために写実的な卑俗さが、彼の美わしいリリズムを傷つけずにすんだ。その特異な象徴的手法が、浮彫のような効果を的確につかんでいる」(p105)と彼の詩の特徴を言い当てているところ。
神と悪魔の相克については、
①ボードレールがくりかえし追い求めた神なるものは、「彼の満足し得ざる肉感の一種の補充とも見らるべきもの」(p91)と言い、また魂と宇宙との照応の際に、霊媒者の役目を果たすのが女性であるとしている。
②ボードレールにとっての悪魔は、自己の外にあって、彼を無限の不幸に陥れる一種の霊であった。ボードレールは神の実在よりも悪魔の実在の方をより感じたという。著者はさらに筆を進めて、「神を・・・自己の内なるものに求めることを、やめなければならない。自己の外なる神のみが、我等を救い癒すであろう。そして神の内に生きる時の自己と、平素の行為に於ける時の自己と、全く異なった二つの自己を所有する愚かさから、逃れる事が出来るであろう」(p65)と書いているが、これは仏教の他力に通じる考えではないか。
③ジャン・コストカという人が『仮面を剥がされたるルシフェル』という本の中で、悪魔は人間の霊魂を殺戮し地獄に引きずり込むのに、人間がキリストよりも悪魔に懐いていることは不思議だと書いているとのこと。同感。
ボードレールの言葉で印象深かったものを列挙しておきます。
生産的集中主義は、老成した人間にあっては、消耗主義にとって代わるべきである・・・自己の蒸発と集中、一切はこの中にある/p36
君臨するために、存在する必要をもたないところのものは神のみである/p78
祈りの中には、不可思議なる作用がある。祈りは、知恵の力の最も偉大な発見の一つである。そこには電気の循環に似たものがある/p79
詩は、芳香あるいは苦味の、至福あるいは恐怖の総べての感情を表出する能力と、これこれの名詞とある形容詞とを結合することや、類似法を用いるか対照法を用いるかということによって、絵画や理科や化粧法の技術と結びついているのである/p148
 外
外  中扉
中扉 

 外
外  中扉
中扉