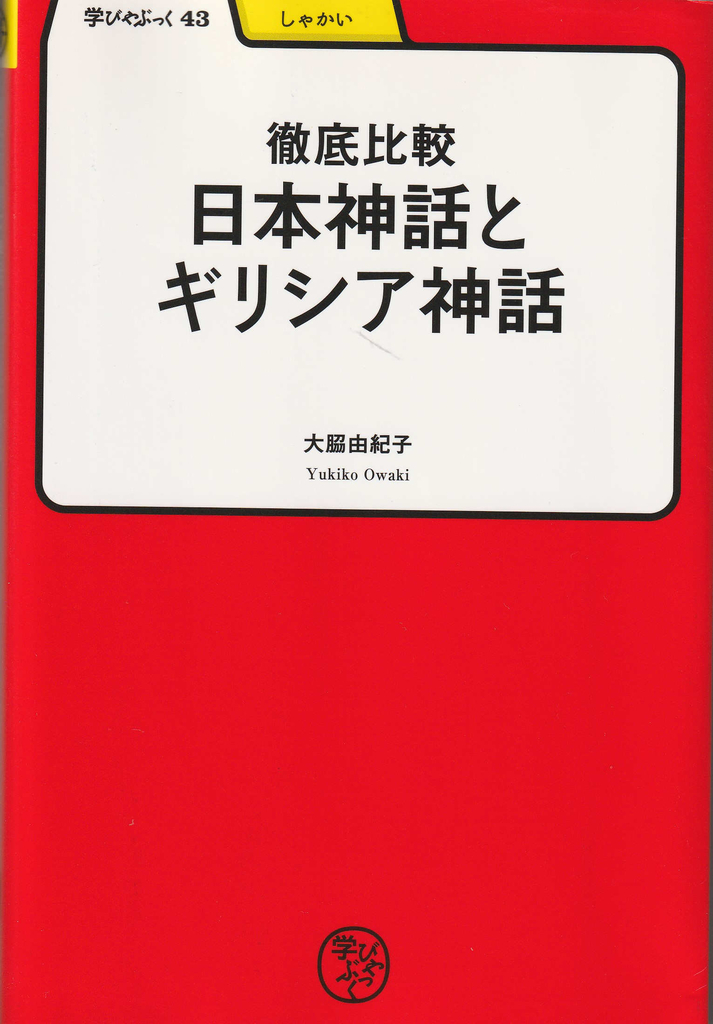吉田敦彦『天地創造神話の謎』(大和書房 1985年)
引き続き、吉田敦彦を読みました。この本は『天地創造99の謎』(サンポウブックス、1976年)に加筆・増補したものということなので、前に読んだ二冊よりは古いものです。オイディプス神話の構造分析や南米ボロロ族やアピナイェ族の神話についてのくだりは『神話の構造』と同じ内容。入門書的な体裁で、見開き2ページでひとつの項目を解説し、各項の冒頭で前項の復習を簡単にしながら次の説明に移る方法は、簡潔さと全体の流れを両立させるうまいやり方だと思いました。
また、世界の神話をテーマごとに区切って考えているのが特徴で、全体は9章からなりますが、大きく二つに分かれ、ひとつは世界の初源についてのテーマ(世界の創造、人類誕生、太陽と月・霊魂・火・死の起源など)、もうひとつは神話自体についてのテーマ(東西神話の類似、神話はなぜ生まれたか)を取りあげています。
一点気になったのは女性蔑視的な視点。とくに、第6章「霊魂は、なぜ生まれたのか」と第7章「女性は、なぜ罪と関係あるのか」に顕著。第6章では、人間の霊魂というものは、天に属する男性的部分と、大地に属する女性的部分に分かれ、男性的部分は天に飛翔しようとするのに、女性的部分が誘惑の手段を使ってそれを阻止しようとしているとするグノーシス神話と、天から来た魂と地下から来た魄が身体の中で結合したのが人間で、汚濁の世界から天上に帰ろうとする魂の要素が強いのが男性で、それを引き留めようとする魄の要素の強いのが女性という中国の魂魄説を紹介し、両者が類似しているが、これが人間存在の真相だと書いています。第7章では、「神に近い生活を送っていた男が、あとから出現した女の犯した過ちによって、苦しみに満ちた生を送った末に死ななければならぬ運命を持つようになった」とか、「なぜ男は女のために一生苦しみ、働くのか」とか妄言を吐いています。吉田敦彦は私よりかなり上の世代なので、戦前の気風が奥深く残っているということでしょうか。
いくつかの面白い指摘がありましたので、我流の要約で紹介しておきます。
①神の意志で、神がなにか言葉を発すると、そのとおりに、天地の万物が生まれたり(古代ヘブライ神話)、神の名前を知るだけで絶大な力が授かったり(日本の伝説)、と言葉の重要性を指摘しているところ。
②卵の中から宇宙が生まれたというフィンランド神話を取りあげ、卵から生物が出現する奇蹟を見て、科学的説明のなかった時代の古代人の想像に思いを馳せているところ。また、卵から雛鳥が出現し蛹から蝶が飛び立つという神秘を前にして人類は霊魂の存在を信じるようになったというスペンサーの考え方を紹介している。
③海に矛をさし入れ海水を攪拌して引き上げた時に、矛の先端から滴った塩水が積もってオノゴロ島ができたという日本神話について、魚を釣るように陸地を釣り上げたという南洋の神話の一変種とする見方と、矛は男根で塩水は精液をシンボライズしており、男性器が創造の源とするインドやエジプト神話と共通しているとする見方を紹介している。
④人間の霊魂を神の息と同一視する観念は、ユダヤ=キリスト教に一貫するとしている。
⑤近親婚のタブーは人類のすべての文化に共通して見られるのに、いくつかの神話では、人類が原初の男女によってなされた近親婚から発生したことになっている矛盾を指摘しているところ。
⑥人類の諸文化の間に優劣の差はなく、人間はいつの時代どの場所においても、つねに偉大で崇高な神性と野蛮で低劣な獣性を兼ね備えた矛盾に満ちた存在であり、その矛盾を解決しようと痛ましい努力を続けてきた。神話はそうした人間の努力の証言だ、と最後に力説しているところ。
恒例により、不思議な神話的想像力が感じられ文章を引用しておきます。
卵・・・割れた殻の上半分は天空となり、下半分からは堅固な大地ができた。卵の黄身からは太陽が、白身からは月が発生し、卵の中のまだらな部分は星に、黒っぽい部分は雲になった/p25
悪魔が神の身体を転がすにつれて、陸地はどんどん面積を増し、しまいには海は陸によってすっかり覆われてしまった/p27
マルケサス島の神話によれば、世界のはじめにはただ海だけがあったが、その上にカヌーに乗って浮かんでいたティキ神が、海底から陸地を釣り上げた/p28
世界が創造されるべき時がくると、この大洋に浮かび眠っているヴィシュヌの臍から、蓮が芽を出し、やがて黄金色に光り輝く一輪の花を咲かせる・・・この蓮の花が大地となり、また万物を生み出す大地女神の女陰ともなって、ヴィシュヌの内にある世界が、現実のものとして創造される/p35
アルメニアの伝説・・・毎年昇天節の晩に・・・岩から、馬に乗り一羽の漆黒の鴉をともなったメヘルという名の巨人が出てきて・・・また岩の中へ帰る・・・割れ目は、巨人が通るときは大きくなるが・・・岩の中へ帰るとまた元通り閉じる・・・かれのかたわらには、たえず二本のろうそくが燃え、また、かれの面前では宇宙を象徴する一個の車輪がまわり続けている。この車輪の回転が止まると、世界の終わりがくる/p51
アイヌの神話・・・悪神は、日の出の時にも日の入りの時にも、太陽を呑もうとして大口をあけるので、神々はその口の中に、朝には狐を二匹投げ込み、夕方には烏を一二羽投げ入れて、そのすきになんとか日神を無事に通過させていた/p70
むかし天には十個の太陽があった。弓の名人が地上の熱さを和らげようとして、そのうちの九個の太陽を射落としたところが、残った一個の太陽は射られることを恐れ、山のうしろに逃げ去り・・・二年間暗闇が続いた/p75