



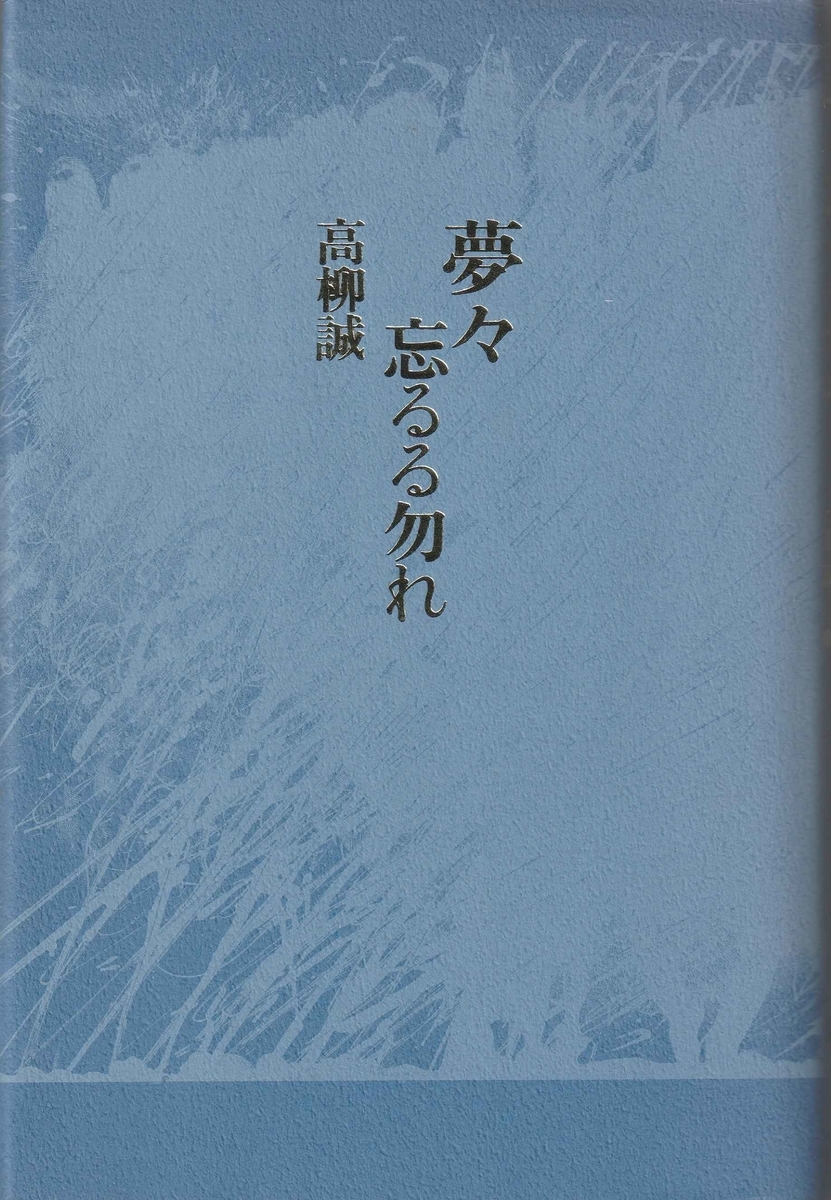



高柳誠『卵宇宙/水晶宮/博物誌』(湯川書房 1983年)
高柳誠『都市の肖像』(書肆山田 1988年)
高柳誠『塔』(書肆山田 1993年)
高柳誠『綾取り人』(湯川書房 1985年)
高柳誠/小林健二(装画)『星間の採譜術』(書肆山田 1997年)
高柳誠『夢々忘るる勿れ』(書肆山田 2001年)
高柳誠『半裸の幼児』(書肆山田 2004年)
高柳誠『光うち震える岸へ』(書肆山田 2010年)
高柳誠『月の裏側に住む』(書肆山田 2014年)
『都市の肖像』や『塔』など架空の世界がテーマになった詩を書いている高柳誠の詩集を、所持している限り読んでみました。随分とありますが、これでも著者の詩集全体の半分にもなりません。折々ランダムに買いためたもので、本格的にはまだ読んでませんでした。一冊の詩集ごとに雰囲気が変わっていて、これほど多様な詩の文体を使い分けている詩人は珍しいのではないでしょうか。
しかし、多様に見えるなかでも、全体を通して、何か共通の特徴らしきものがあるように思います。稚拙な感受性しかない私の素朴な印象ですが、下記に。
①例外はあるが、おおむね、それぞれ独立した詩篇が集まり、詩集全体としてひとつの完結した世界を作り出すような緊密な構造を持っている。
②基本的に散文詩人のように思う。一篇ずつの詩は分かりやすく、作品として整った感じを受ける。悪く言えば、飛躍的で超越的な(あるいは破壊的な)詩としての発想よりは、筋道をどこかで保とうとしているやや常識的な散文の論理が優っている気がする。つまり読者に詩文の先が読めてしまうようなところがある。
③筋道を断ち切る手法として、前文をすぐ否定したり、事物が本来の機能をしない状態で描かれるなど、期待を裏切る叙述が採用されており、そこでは不条理感を醸し出すことに成功している。
④一人称で語る詩が多い。独白的口調が劇的なトーンと重々しさを醸し出し、内面の思念の揺らぎを表現している。
⑤とくに初期の詩集には、観念的抽象的な発想の詩が多く、宇宙や物理に素材を得たり、論理的な叙述法が採用されている。
これらの詩集のなかで、私の好みにマッチしたのは、順に、『塔』、『夢々忘るる勿れ』、『都市の肖像』、『月の裏側に住む』といったところです。
『塔』で何がすごいかと言えば、物語の枠組みがはっきりしていることと、モノローグ的な語りの重々しさでしょうか。とくに冒頭の連詩「塔」では、「周囲の闇は一層その謎を孕み、潮の香りに混じって獣の死臭めいた匂いが色濃く漂ってきた。その時、何ものかが私の前を素速くよぎる気配がした」(p9)、「階段の上方で人影が動いた」(p13)、「上方で靴音とともに扉のきしむような音がした」(p17)、「上方で突然、鳥の叫び声とも悲鳴ともつかない声が挙がった」(p21)というように、何かの予感が継続的に語られますが、これはまさしく象徴詩の技法で、マラルメの散文詩を思わせるところがあります。
4番目の連詩「島」はとくに私好みの作品で、一級の幻想詩篇となっています。「漆黒の川面を一艘の小舟が漕ぎ上って」(p74)来た男が、島の中央にある廃墟のなかで倒れ込みそのまま眠りこむという冒頭の一篇があり、次に、ある男が、泥を捏ねて人形(ヒトガタ)を作るが、どうしても左足の第二指が欠損することが漢字とカタカナ交じり文で叙述され、その二つの筋書きが交互に語られながら進行していきます。「目を開くと・・・なぜ自分はここにいるのかという疑問が頭を掠めた」(p79)という小舟の男は、島人から神の使者と恐れられ供物をそなえられますが、その足跡には左足の第二指が欠けています。一方、人形に意識が宿ると、人形師は持てる知識のすべてをその人形に教え込み、小舟に乗せて現世に送り出しますが、それと同時に人形師の身体は泥に溶けてしまいます。第一の世界と第二の世界がつながる予感を残して、また物語の終わりが初めにつながる形で詩篇は閉じます。
『夢々忘るる勿れ』は、夢というか悪夢の世界を描いた詩篇群からなっています。なかでも秀逸なのは、丸太となった父を背負っての旅の途中、宿で修学旅行の高校生集団の枕投げに遭い、丸太の父が嘲笑の的になっているのを救い出さなければならないのに、自分は少年時代からの憧れの女優に乳首を押しつけられ手を引かれてホテルへ向かうというジレンマに陥る「父の木化」、夜更けに若者たちに叩き起こされ、両脇を抱えられて行った先には、大怪我をした若者が居て、どうやら自分が医者と見なされているらしいが、今さら引き返すことができず、あてずっぽうに治療をしているうちに傷口が女陰に見えて狂乱に陥る「医師」、砂粒が豪雨のように降り、外に出るときはゴーグルをつけねばならず、交通機関も通信網も機能しなくなり、電気水道も使えなくなり、食糧も枯渇し、最後は眠りの中にまで砂が侵入してくる「砂嵐」の3篇。
次点としては、意味不明の文字による落書きが見つかって以来、徐々に世界が侵略されていく「落書」、居ないはずの兄からいろんな名前の弟となっていろんなことを命じられる「兄」、雨の日も雪の日も一本のロープを渡り続けていた父がある日部屋の隅にうずくまり痩せ縮こまって見えそして消えたという「ロープ」、小学校の同級生らと一列縦隊で歩くのが印象深い「夕焼けのカラス」、それまで聴衆全員を物語の世界に引き込んでいた語り部が突如沈黙し、続きはここにいる真実の語り部からと、私の肩に手が置かれる「語り部」の5篇。
『都市の肖像』はこれらの詩集のなかでは、もっとも架空都市譚にふさわしい内容です。市庁舎、時計台、動物園、図書館、運河、病院、庭園、露地、飛行場など、都市を構成する34カ所が一つずつ語られていきます。「科学館」のなかで、学説について、「正しいか正しくないか・・・よりも・・・夢想力、知的快楽度、美的陶酔度―それらこそがすべて」(p25)という判断の尺度が示されていましたが、これはこの詩集の原理とも言えるでしょう。あり得ない現象、奇異な現象が語られています。その施設の本来の機能がまったく機能していなかったり(「郵便局」や「計測所」)、あるいは本来の機能とは別の動きをします(「時計塔」、「遊園地」)。それがもったいぶった口調で語られるところに、どことなくユーモアのセンスも感じられました。
面白いと思ったのは、廃墟となり霧を噴き上げているだけの「市庁舎」、氷りついた時を少しずつ溶かしているというどこから見ても正面を向いている「時計台」、望遠鏡を覗くと巨大な目がこちらを窺っている「天文台」、読むそばから文字が群れをなして飛び立っていく「図書館」、見る人ごとに映像が異なるが自分の経験か夢か誰かの記憶か分からなくなってしまう「映画館」、人が入ると希薄になり出れば元に戻る「広場」、人々の記憶から消え去りそうになると出現する何を記念して建てられたか分からない「記念塔」、老人が知識を捨て智慧をつけようとして、智慧まで至らず無知の状態のまま、日がな一日無邪気に遊んでいる「学校」、踏み込むといつも驟雨に襲われ常に傴僂(せむし)が後姿を見せている「庭園」。
本体の表紙を飾っているモーリッツの銅版画が素晴らしい。

『月の裏側に住む』は、とくに前半部において他の詩集にはない特徴があります。一種の駄洒落のように言葉尻を捉えて話を展開し、そのなかで少しずつ言葉を変奏しながら、時折自論を挟みこんでいます。単なる言葉遊びにだけ終わらない不条理な不思議な世界が造型され、またそれを真顔で論じているところに一種のおかしみが漂っています。例えば、冒頭の「柔らかい梨」を例にとると、「柔らかい梨があるとする。いや、現に今、柔らかい梨がここにある。実際にあるにもかかわらず、『あるとする』という一種の仮定法で語ろうとするのは、むろんそのことに意味があるからだ」という理屈っぽい文章で始まり、「問題は、意味を、果皮と取るべきか、果肉と考えるべきか、果芯とするべきか」という言葉遊び風の展開があり、次第に駄洒落の開陳に向かって行きます。「梨自身が存在の意味を失い、梨くずし的に崩壊していく・・・意味の側からのなんの反応もない状態で、つまりは梨のつぶてで・・・その本質の保持を梨とげることであるはずで・・・その行為に意味のある梨にかかわらず・・・結局、柔らかい梨自体、洋梨と見なされてゴミ箱に放棄されるしかないのだ」という風に展開していきます。
「夕焼けの底が抜けた」という底について思弁を展開する「夕焼けの底」、頭の中に鳥を飼っているという「叔父さんの鳥」の2篇はとくに秀逸、次点は、柱時計の逆ネジを巻くと時間が逆に流れることについて語る「逆ネジを巻く」、文字通りのいろんな巨頭が集まる「世界巨頭会議」、手のあれこれについて考える「負け犬の手」、夜の白茶けた闇が目蓋の裏の闇に流れこんできて眠れなくなる「反睡眠症候群」、体の奥深くにまかれた種子がやがて見えない木に成長する「不可視木の影」、僕だけが知っている父の翼に憧れる「父の翼」の6篇。
他の5冊の詩集は気に入った順から書くと、スペインらしき海外の体験が軸となっていて、落ち着いてしっとりとした文体で随筆集のような味わいの『光うち震える岸へ』、これもイタリア、ギリシアあたりの素材をもとに、高柳にしては珍しく改行詩の体裁をとりながら実際は散文叙述的な『半裸の幼児』、古代の血や太陽に関する古い信仰、習俗が語られ、神話を彷彿とさせる『綾取り人』、観念的に過ぎる『卵宇宙/水晶宮/博物誌』、カタカナ言葉がちりばめられ、なにか上滑りの印象を受けてしまう『星間の採譜術』。