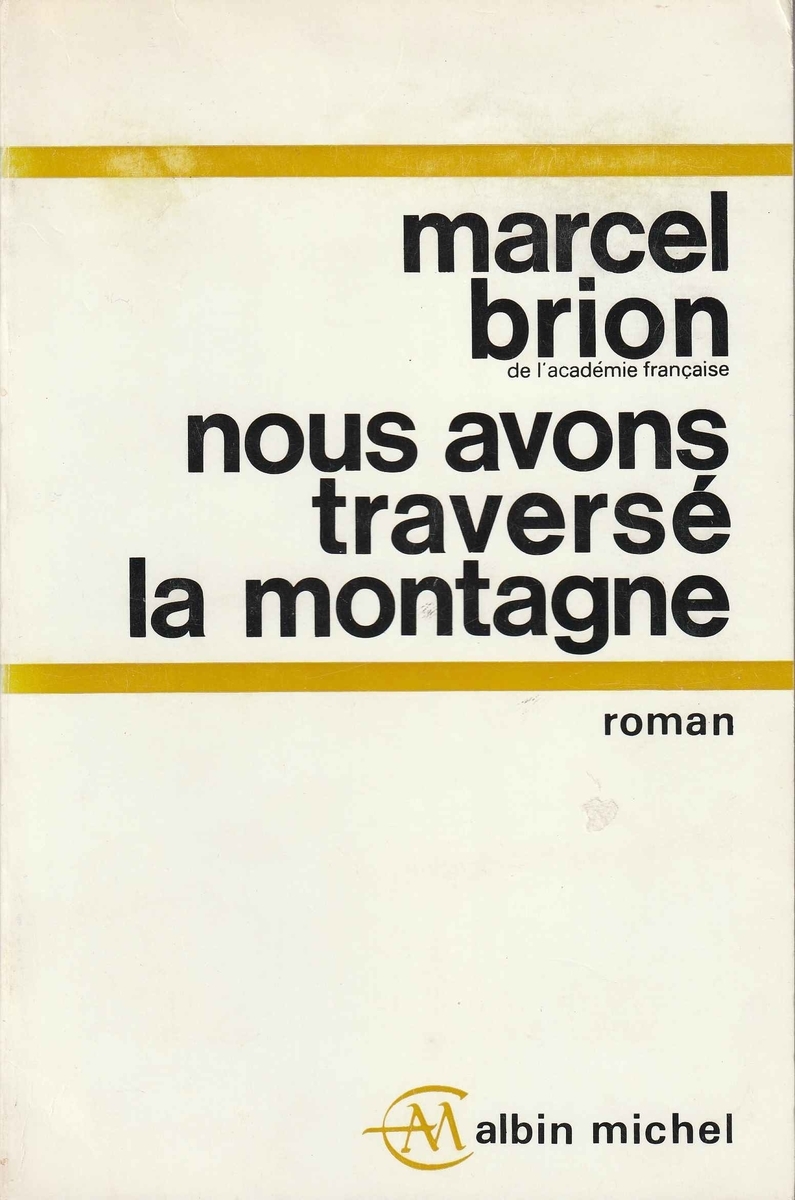
marcel brion『nous avons traversé la montagne』(albin michel 1972年)
引き続いてブリヨンを読みました。前回読んだ『Les Vaines Montagnes(辿り着けぬ峰々)』の序文で、奥さんのLiliane Brionが本作に言及して、ブリヨンの最上作品のひとつと書いていましたが、この小説は、『Les Vaines Montagnes』とテーマも構造もよく似ています。急峻な山の向こうの世界に憧れてその山を越えようとするところ、またいろんなエピソードを語り継ぐ手法など。「traversé」は普通なら「越えた」と訳すべきでしょうが、結局山の中腹の穴を通り抜けることになったので、「通り抜けた」というふうにしました。
話しの大枠は次のようなもの。ある灼熱の土地の旅籠に居合わせた旅人たちがその後行動を共にし、目的も不確かなまま、現地のガイドやポーター、それに占い師まで雇って旅を続けるが、途中、超自然的現象のなかで一人また一人と脱落し、ガイドも失踪し、占い師もメンバーに呪いをかけながら空に消える。ついにリーダー的存在だったベルグもクレヴァスに消え、残った者たちで急峻な氷山を越えようとするが…。最後は消えていた死者たちもみんな集合して新たな旅に出る。
次のような話が途中語られています。( )内は話者。他にも短い挿話がたくさんありましたが省略。
冠を剥奪された女王の伝説(旅籠の主人):昔、冠を剥奪され追放された女王がこの旅籠で英雄と出会い、結婚して失った国を奪還する。女王が唯一持ち出したという瑪瑙の鉢が残っており、旅人たちはそれで古いワインを飲む。
もぬけの殻の町(わたし):旅人たちが訪れた町は、温かい食事の用意があるなど、つい先ほどまで居た形跡を残しながら誰も住んでいなかった。勝手に家に上がり込み寝ると、翌朝、町民たちが戻ってきていたが旅人たちには気づかない。
大昔の種族の遺跡(わたし):太古の種族が岩にさまざまな図柄を彫りこんでいた。旅の一行がそこで寝るが、女の絵の上で寝ていたメンバーは淫夢魔に襲われたようにげっそりと窶れていた。
昔絵で見た天使と出会った黒い女神の祭(ピルジェ、イゴール):少年の頃イタリアの美術館で天使の絵を見て以来、その蒼い顔をした天使に憧れていたが、長じて、白い女神が黒い女神と年1回合体するという奇祭の儀式に立会ったとき、生贄となり殺されようとする少年がその天使にそっくりだった。
舟の上の女性と交わる奇祭(グラーム):南洋の黒い女神を信仰している村で、湖の何艘かの舟に赤いベッドがあり女性が寝ていて、男たちがその舟を目指して泳いでいくが、途中怪物が現われて湖底へ引きずり込む。イゴールも飛び込み12日後に戻ってきたが、女性と交わった後の記憶はないと言う。
尾行してくる幽霊騎馬隊(わたし):旅の一行につかず離れず併行してくる騎馬隊があった。いつも夕暮れ時の一瞬姿を見せるのだった。ついにある日、対峙し、騎馬隊が襲ってくるが、一陣の風が通り過ぎただけだった。
女騎士に連れていかれた湖の傍らの町(ペテルセン):幽霊騎馬隊の女性隊長だけが戻ってきて、ペテルセンは彼女について行き、数日後髭ぼうぼうで戻ってくる。地底の湖辺の町で何年も過ごしたが、ある日市場で、金の水差しの胴に描かれた細密画を見ると、そこに自分がいて呼びかけられたと言う。そう話して数日後また姿を消した。
河に駿馬もろとも飛び込んで溺れた皇帝の話(渡し舟の船頭):鉄の部隊とともに河にやってきた皇帝は、どうしても向う岸に渡りたいと言う。川沿いに進むことを主張する隊員たちが止めるのも聞かず、水嵩の増した河に入って行き、愛馬の黒馬とともに沈む。
石けり遊びの図を黒板に書かされる夢(わたし):教室の黒板の前に立たされ、子どもたちの石けり遊びの迷路の図を書けと命じられる。窓から子どもたちがどうなるかと見ている。子どもが頭上に持っている飛行機を見て、仕方なく飛行機の絵を描いた。
続いてテセウスとミノタウロスが鏡の部屋で戦う夢(わたし):卒業式の式典でテセウスとミノタウロスの物語が演じられている。鏡の部屋なので自分の鏡像と闘っているとも見える。私は剣を避けながら鏡にしがみついている。どうやらここは石けり遊びの枠のなかのようだ。
逃亡する占い師(わたし):高台に登る途中に、架空の動物も含めさまざまな動物の石像群があり、それらの像を足場にして攀じ登った。占い師は死者の国へ行って最上のルートを聞いてきたはずなのに教えてくれない。ガイドたちが占い師を縛り付けて吐かそうとすると、大音響とともに縄が解け、占い師はグリフィンの石像に乗って空高く舞い上がって行った。
地上と地下が対称的な形をした寺(ピルジェが商人から聞いた話):寺を建築中に隕石が落ちて穴を開けた。それをきっかけに地下にも地上と対称の寺を作る。降りて行くほどに部屋が小さくなる形をしている。世界の終りの日が来ると、地上の寺は崩れ落ち地下の寺は埋まるという。
若き日のピアノのレッスンの思い出(ヴェンゼル):占い師から呪いをかけられたヴェンゼルは日に日に弱って行き、動けなくなったので、牧童のテントで世話になる。そこでピアノの先生からいつも間違いを指摘されていたことを思い出す。それはシューベルトの遺作のソナタだった。
族長の墓(わたし):丘の麓に墓が立ち並んでいたが、そのなかでひときわ立派な墓があった。どうやらかつての族長の墓らしい。子どもから大人になるまでの姿、前世の様々な生き物の姿の像に囲まれていた。
ベルグの失踪(作者):氷に覆われた高台でキャンプしていたとき、ベルグは子どもの頃飼っていた小犬の鳴き声を聞いたように思って外に出た。その小犬は大きな鳥に襲われ、幼いベルグは必死で鳥と格闘したが攫われてしまった苦い思い出がある。小犬について穴のなかに入り頭を撫ぜていると穴が閉じた。
小人が広げる絨毯の上に乗って見る幻影の庭(グラーム):夢のなかに身体もろとも吸い込まれグラームはベッドから消えたが、戻ってきて見た夢の話をする。小人が広げた絨毯の上に乗ると、そこは十字路で池と花壇があり、果てしない平原が広がっていた。外へ出ろと言う小人の声で出ると、そこは石けり遊びの枠のなかだった。別の枠に移ると、ピアノを前にしたヴェンゼルがいたり、テセウスとミノタウロスの部屋だったり、ある男を追いかけてあと少しで列車が出て行ったり、帰るホテルを忘れてさまよったりし、最後に天文学者たちが群れる観測所で訳の分からない地獄に落とされたように感じ、ようやく階段を見つけ登り詰めた。
夢の在り方が一つのテーマになっていると思われます。最後のグラームの夢で起こったように、夢のなかに身体も入りこんで、そのままベッドから消えてしまうということが起こります。またすべて夢と言ってしまえばそれで終わりですが、夢を操る小人がいたり、見知らぬ男が夢のなかにまで入りこんで追いかけてきたりします。物語の最初から最後まで、石けり遊びの枠という言葉がよく出てきて、その枠のなかで幻を展開して見せますが、これも夢の一種と言えます。
もうひとつは、ペテルセンが語る地底の町の話に、時間感覚を喪失する話が二種類見られることです。ペテルセンは地底の湖の町に何ヶ月いや何年も行っていたと言い窶れ果てていますが、実際は1週間足らずでした。これは浦島物語の逆パターン。また市場で見つけた水差しの腹の部分に細密画が描かれていて、自分自身の一生がそこで展開しているのを見ます。これは邯鄲の一炊の夢と似ています。
前にも書きましたが、ブリヨンの作風は、一つの詩を冗舌と反復によって大きく引き伸ばして長編に仕立て上げている感じがあります。同じような詩的情緒が繰り返される一種のマニエリスム(マンネリズム)と言えるでしょうが、バロックやマニエリスムにありがちなけたたましさは感じられません。「夜」、「光」、「沈黙」、「影」などの詩語は、若いころには共感しても、そのうち単純な技巧に思えて忌避するようになりますが、私のような歳になると、使い古された詩語であっても嫌な気がしなくなっているので、静謐な雰囲気に浸れるのが心地よく感じられます。
日本の弓道について、「矢はそれ自身が的である」という禅問答的な言葉とともに、言及がありました(p269)。