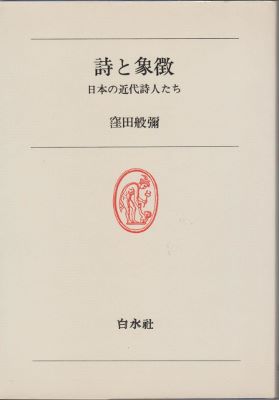
窪田般彌『詩と象徴―日本の近代詩人たち』(白水社 1977年)
全般的に、前回読んだ随想風の『フランス文学夜話』に比べて濃密な印象があり、文章が論理的でしっかりした評論が揃っています。全篇を通じて日本の詩がテーマになっており『日本の象徴詩人』の続編と言えるでしょう。「日夏耿之介と『ゴシィック・ロオマン詩体』」が重複している以外にも、朔太郎、小林秀雄、吉田一穂、上田敏など共通して論じられている詩人が多いのは、それらの詩人に対する感心の強さを物語っています。
およその時代順に詩人にスポットをあてたⅠ〜Ⅲ章と、時代を大きくとらえ海外詩との関係を論じたⅣ章に分れ、18篇の評論が収録されていますが、とりわけ印象に残ったのは、Ⅰ章の「『薔薇の詩人』大手拓次」「永井荷風 生きている過去」、Ⅳ章の「大正期におけるフランス詩」の3篇。
大手拓次が日本語の音感にたいへん敏感だったこと、まだ無名のうちから、自分が日本における最高の位置にいると手紙に書くぐらい自信があったことなどを知りました。詩の雰囲気が朔太郎とよく似ているので、大手拓次が影響を受けたと思っていたら逆で、朔太郎が拓次の影響を受けたと告白しているのには驚きました。詩の心構えについて、「もっと破格に、大胆に、あだかも自分の血と肉とを叩きつけるようなものをつくってゆく事が最も正しい経路です。詩の筋とか意味あいなどは或程度まで無視するぐらいがよろしいのです。・・・あなたの其時の心持のリズムをあらわすべき言葉をさがしもとめることです。しかしリズムは其人自身のものでなければならぬ。模倣や追従であってはならぬ。言葉の音を何より重んずる事が大切です」(p53)と友人に書き送っています。あの独特の世界はこうした決意のもとに作られていたんですね。
「永井荷風 生きている過去」は、このところ読んでいるレニエが取りあげられているので、面白く読めました。荷風がいかにレニエやローデンバッハから養分を得て、自分の作風に生かしているかがよく分かりました。過去に対する強い愛着が古い器物や古い家への執着となって現われたり、粗野で愚劣な社会への嫌悪を感じつつも正面から反抗することがなかったりするところに、荷風とレニエの共通点を見ています。レニエの詩が『噴水の都』序詩と『翼あるサンダル』の「宣言」が引用されていましたが、いずれもすばらしい。
「大正期におけるフランス詩」では、上田敏が雅語や漢語を駆使した『海潮音』でのみ注目されていることへの不満を述べ、『牧羊神』での柔軟で新鮮な訳詩ぶりを高く評価し、また同じ観点で、永井荷風の文語を使用しながらも柔らかな印象を残す『珊瑚集』の新しさや、堀口大学のエスプリ・ヌーボーの軽妙な律動を感じさせる訳詩を称揚しています。『牧羊神』が室生犀星や梶井基次郎に、『珊瑚集』が三木露風、佐藤春夫、柳沢健、生田春月、川路柳虹に、『月下の一群』が三好達治、中原中也に多大な影響を与え、大正期の訳詩集がその後の日本詩を大きく発展させたことが指摘されていました。
あらためて魅力を感じた詩人としては、安西冬衛、吉田一穂の二人。この二人の詩は何と凝縮されてかっこいいことでしょうか。それに比べて瀧口修造は言葉が粗雑、西脇順三郎の晩年の詩も言葉が薄っぺらでだらだらと感じられました。ただ西脇順三郎にフランス語詩集があることを知り、それが初期の『Ambalvalia』のギリシア的抒情を思わせると書いてあったので、ぜひ読んでみたいと思いました。詩論については、吉田一穂、瀧口修造の詩論は少なくとも引用されている部分はあまり関心しませんでしたが、西脇のヨーロッパ文学論は面白そうに思えました。
著者が小林秀雄に対して、「昔はこんな小林流の啖呵に感心したものだったが、いまは舌足らずの小僧っ子に出くわしたようで、むしろ生理的な不快感を味わうことのほうが多い」(p155)と感想を述べているのは我が意を得たりですが、一方で、やんちゃな小僧っ子というのは、自分に誠実な態度とも言える気がします。
「フランス語を聞くことが全く駄目な私」(p164)と告白しているのには共感を覚えると同時に、フランス語の先生なのに素直にさらりと言ってのけるその大胆さに驚いてしまいました。