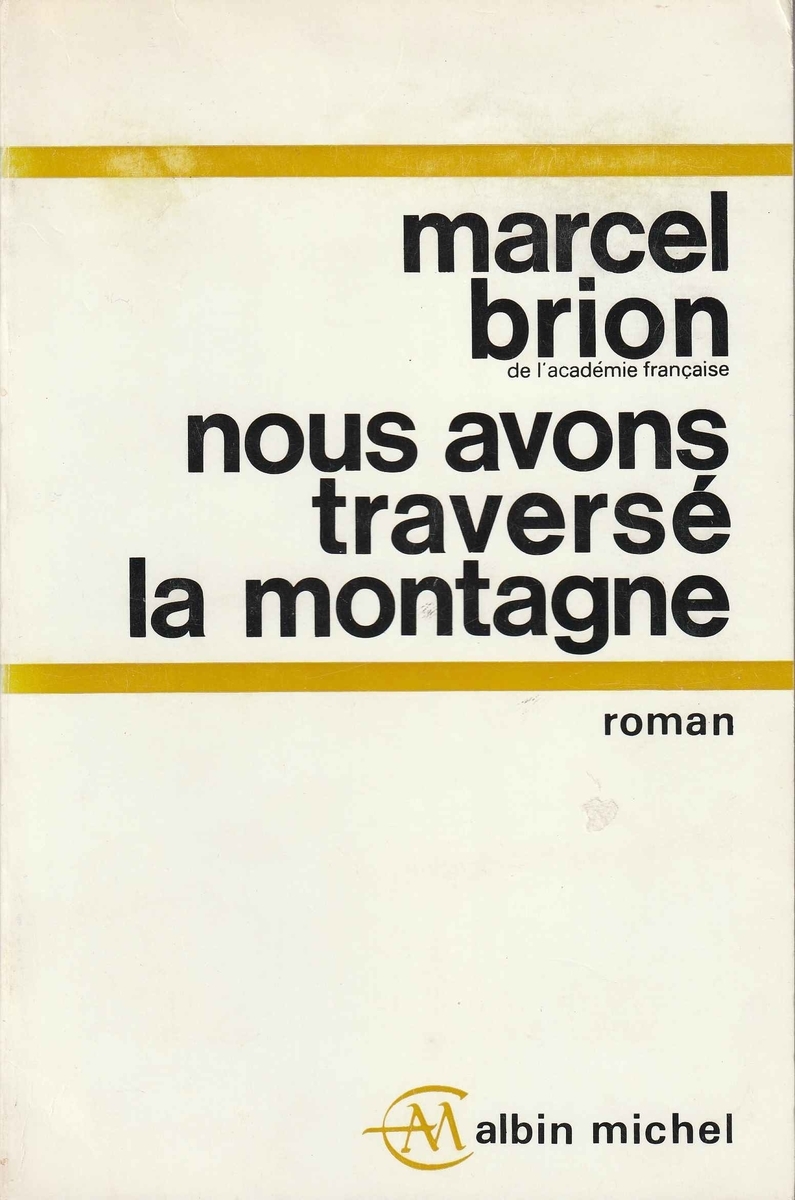Jean Lorrain『Venise』(La Bibliothèque 1997年)
今回は、90ページほどの薄っぺらい本ですが、やたらとイタリア語やヴェニスの建物の固有名詞が出てくるので読みにくい。1905年に「絵入り雑誌」に寄稿したヴェニスについてのエッセイと、1898年から1904年にかけて、母親や友人宛てにヴェニスから送った手紙が11通収録されています。いずれもヴェニスを褒めたたえた文章が連なっています。
ヴェニスの風光の美しさ、とくに黄昏の景観、そのなかを滑りゆくゴンドラ、歴史の積み重なった都市の栄光とその悲哀、運河と小路でピラネージの迷路のように入り組んだ町並み、教会や宮殿の建物の壮麗さ、それが沈み行き崩れ落ちつつある廃墟の美、美術館や教会の絵画の素晴らしさ、男は敏捷で女性は窶れたように美しいヴェニス人、それらが詩の引用をまじえた美文調で綴られています。
ヴェニスを愛した文人・芸術家として、エッセイのなかでは、モーリス・バレス、バイロン、ミュッセ、ワーグナー、ズーデルマン、ダヌンツィオ、手紙ではユーグ・ルベルの名前が挙がっていました。ヴェニスと言えば、われわれの思い浮かべるのはトーマス・マンとかアンリ・ド・レニエですが、彼らはロランより時代が後になるわけです。とくにレニエは、ロランが目をかけて文壇に紹介した師弟関係とも言うべき作家です(だと思う)。
ロランは1898年に初めてヴェニスへ行き、その後1901年、04年とヴェニスに滞在しているようです。レニエは、年表(Régnier『ESCALES EN MÉDITERRANÉE』の附録)を見ると1899年から1907年にかけて6回ヴェニスに滞在しています。ほぼロランと同時期にヴェニスを体験している様子ですが、有名な『ヴェニス素描』の出版は1906年と少し後になりますし、ヴェニスでの生活を綴った『L'Altana ou la vie vénitienne』も1928年の出版です。
このロランの『Venise』を、『ヴェニス素描』でのレニエの散文詩と比較してみると、具体的な説明と描写があり、筋道だっていて、ヴェニスのレポートといった感じ。ゴンドラレースで町が湧く様子、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が来訪したときの歓迎ぶり、絵画や彫刻の事細かな感想、建物の崩壊の報告も詳しく、離島の紹介も忘れていません。また大勢の観光客が押し寄せるのを苦々しく眺め、運河を埋めて道にし、アスファルトにするという近代的計画を痛罵しています。が一貫しているのは、そこに世紀末的な退廃の味が沁み込んでいることです。
古きヴェニスへの憧れを切々と綴っていますが、それは単に16世紀から18世紀にかけての古い時代を懐かしんでいるというだけではなく、ローマ時代から培われ、ルネサンスで花開いたイタリア文化、フランスの先陣としてのイタリアへの憧れがその背後にあるのではないでしょうか。とくにヴェニス派の画家たちへの傾倒がありありとうかがえます。グアルディという知らない画家の名前があったのでネットで調べてみると、「サン・マルコ湾」など奇想画を描いている人だと分かりました。また一人好きな画家が増えました。
手紙の宛先の友人というのは、オクターヴ・ユザンヌ(3通)、ギュスターヴ・コキヨ(1通)、「友へ」としか書かれてないもの(3通)でした。ユザンヌはボードレール論などで知られる愛書家で、ロランが初期代表作『ブーグロン氏』を書くきっかけとなったオランダ旅行を案内し、ロランに旅の楽しさを教えたということです。コキヨという人は知りませんでしたが、美術評論家のようです。手紙には、幼友達やマラルメなど付き合いのあった文人たちが次々と亡くなっていくのを嘆いていますが、それがまたヴェニスの崩壊と響きあっているような気がします。
『Venise』でこれほどヴェニスの熱い思いを語っているのに、ジャン・ロランの存在がマイナーなせいか、ヴェニスについて言及している多数の文人名を網羅した平川祐弘『藝術にあらわれたヴェネチア』にも、ヴェニスに魅了された文学者を紹介した鳥越輝昭『ヴェネツィア詩文繚乱』にも、ジャン・ロランの名が記されていないのは、とても残念です。