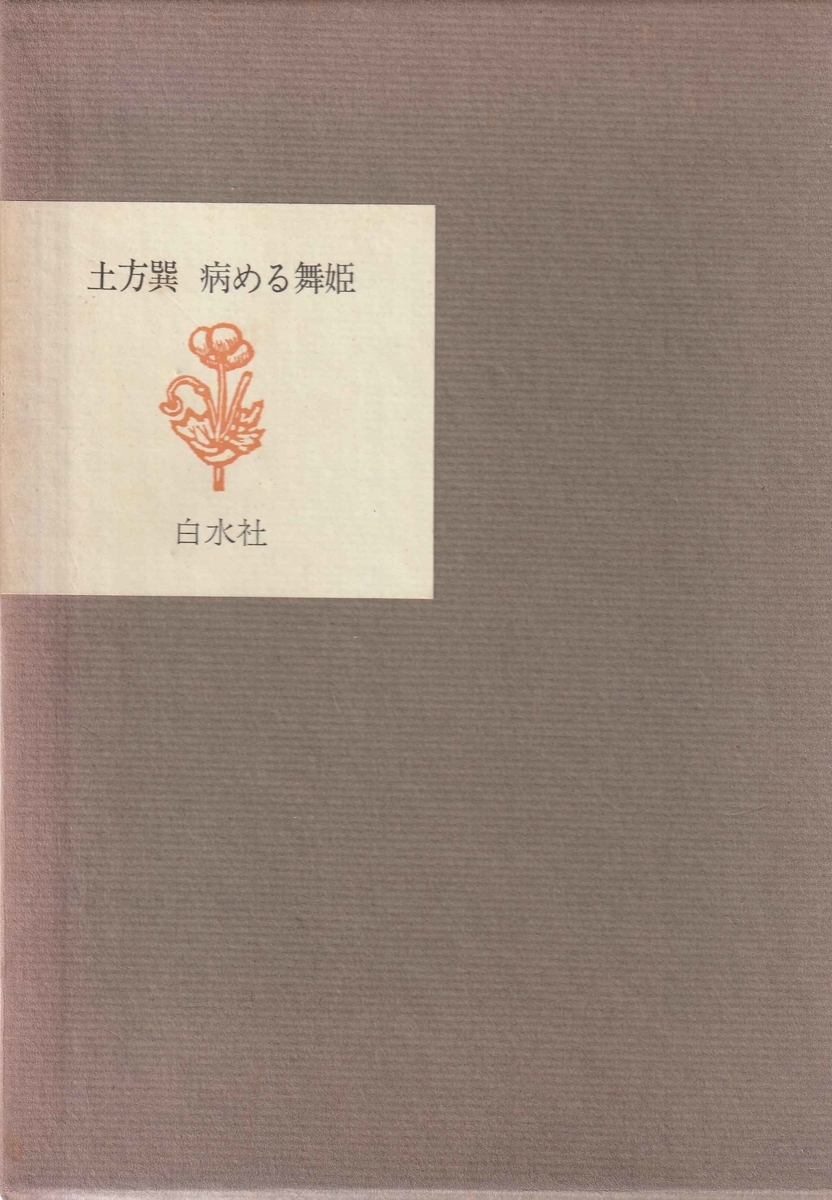 函
函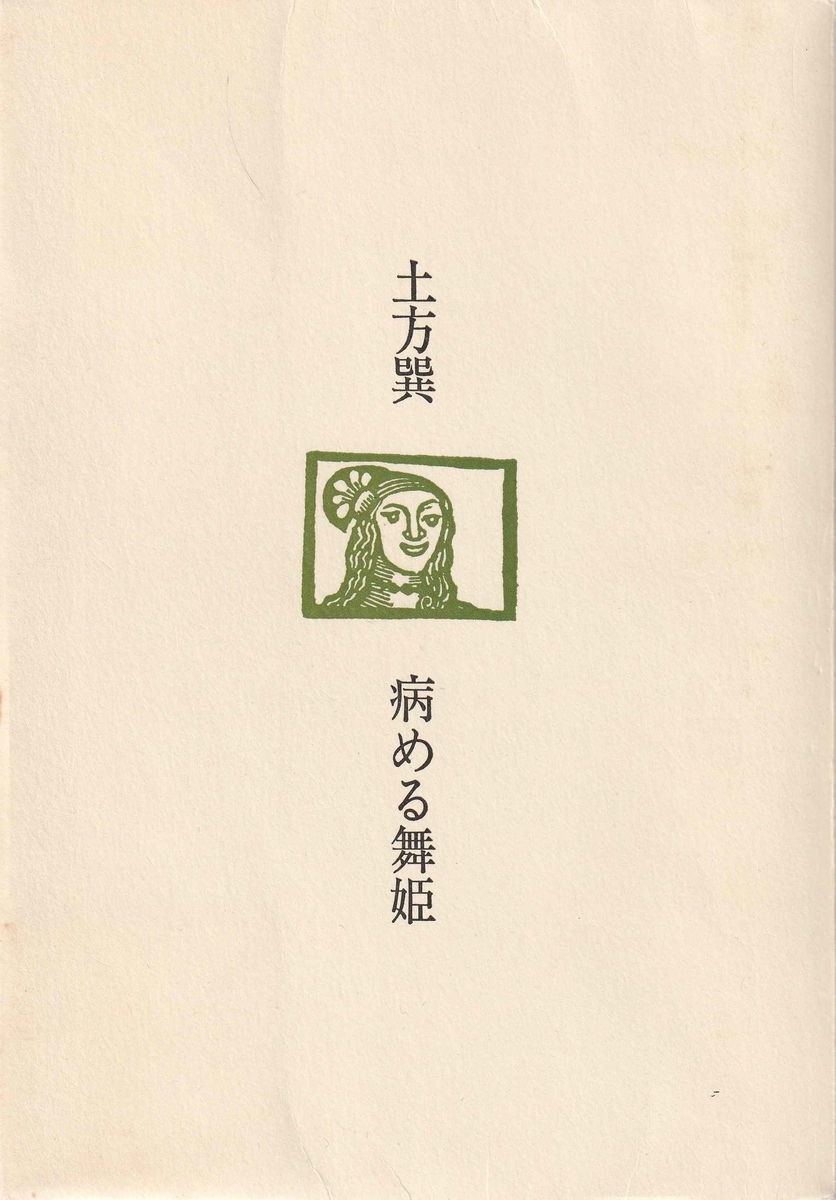 中
中

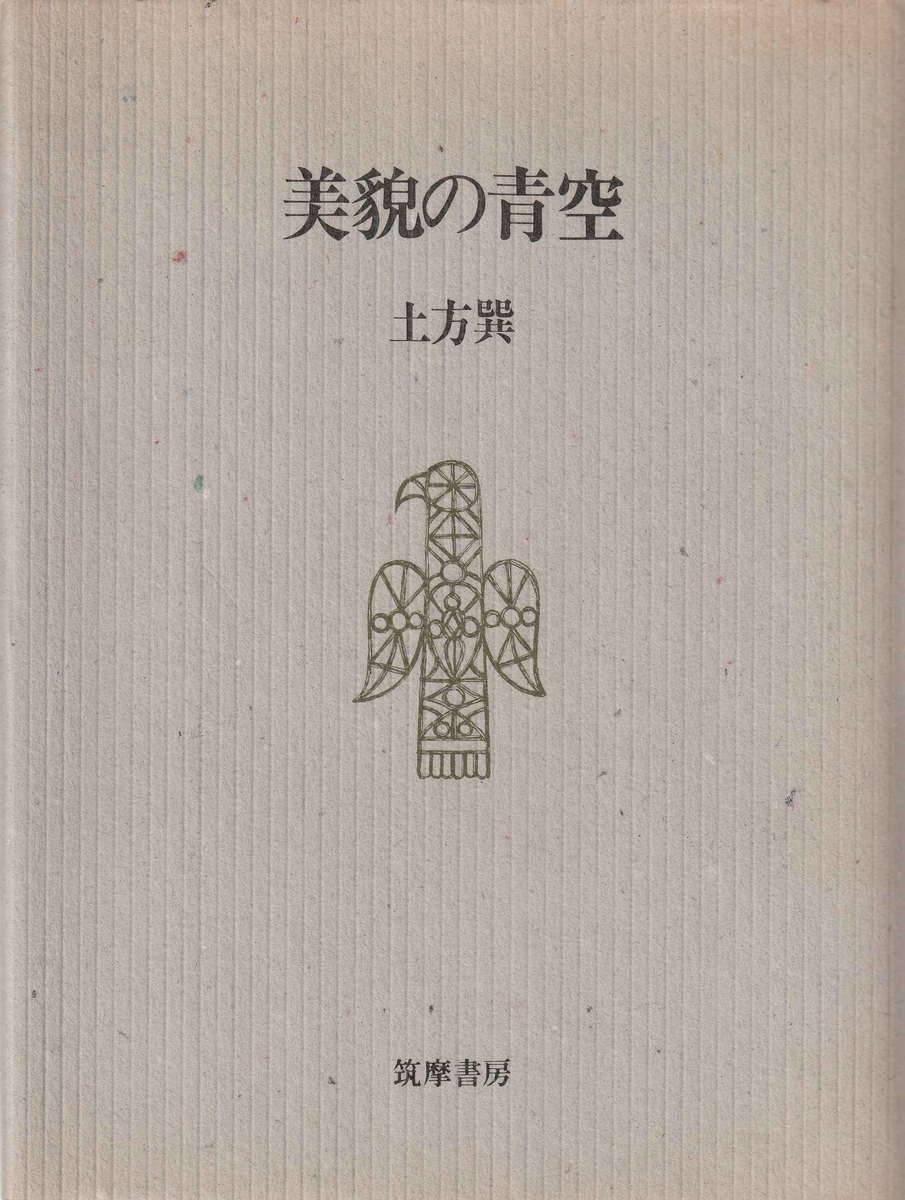

土方巽『病める舞姫』(白水社 1983年)
土方巽/合田成男ほか「極端な豪奢・土方巽リーディング」(UPU 1985年)
土方巽『美貌の青空』(筑摩書房 1987年)
土方巽/筆録吉増剛造『慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる』(書肆山田 1992年)
前回読んだ吉岡実とも親交が深く、『吉岡実詩集』の推薦文も書いている土方巽の文章を取り上げます。学生のころ京都で土方巽の「燔犠大踏鑑」という舞踏公演に接したことがありましたが、パンフレットに土方巽の奇妙な文章が載っていたような気がします。それもあってその後の土方巽の書いたものや談話に注目していました。今回取り上げたのは、土方巽のあの独特の文章には、アジア的奇想を讃えたボルヘスも真っ青になるようなアジア的イロジスムが横溢していると考えたからです。これらの文章が発表された頃の詩壇の反応については、サラリーマン生活に明け暮れていて知りませんが、生半可なシュルレアリスム詩人を凌駕するものだと思います。
『病める舞姫』は、自伝的要素が濃厚で、少年期の田舎での思い出が主軸となった書下ろし?の作品。「極端な豪奢・土方巽リーディング」は雑誌の土方特集で、「犬の静脈に嫉妬することから」の再録と、土方へのインタビューの他、論者の対談や評論、友人たちの感想を収めたもの。『美貌の青空』は土方の死後、土方巽があちこちに書いた文章を、種村季弘、吉岡実、澁澤龍彦らが編集しなおしたもの。『慈悲心鳥がバサバサと…』は映画撮影のなかで土方巽が語った言葉を文字に起こしたもの。『病める舞姫』と『美貌の青空』に収められた文章が圧巻です。
土方巽が展開するイロジスム(非論理)については、下記のような感想をもちました。
①何が書いてあるか意味がつかめないが、文章としてはおかしくはない。シンタックスの構造は維持されているし、音声言語としてのトーンも温存されている。何が変かと言えば、言葉が通常のようにつながって行かないのである。
例えば次のような文章。「もし仮にこういうものを表情の海と呼ぶならば、そこに立つ彼がいなければ海は無表情の海と化すと狭義に断定してもいい」(『美貌の青空』p173)。彼とは唐十郎のことだが、「彼」を「波」と置き換えると何とか意味が通じる文章となる。もうひとつの例を挙げれば、「劇場に耳を残したまま帰路につくていたらくの私」(『美貌の青空』p52)の「耳」を「傘」に入れ替えてみればなんてことはない文章だ。もうひとつ挙げると、「あなたは紙を折檻したり、豚にアイロンをかけたりはしないだろう」(『美貌の青空』p224)では、「紙」と「豚」の入れ換えが行われている。
②意味がつながっていかない構文の中では、単語の果たす役割が大きいこと。テーマに近い単語が散りばめ嵌め込まれている。例えば、吉岡実詩集の推薦文では、「比類のない凄惨な眼球によって詩刑に処せられるものは、剥製にされた光の間に置かれる音楽や絵の器であり、身ぐるみ剥がれる万象の姿態から、その始まり、その羞恥にまで及んでいる。蒸留される幻もここでは硬く艶やかである。一挙の超越が切り結ぶ実像がここに置かれて、一切の狼藉は跡かたもない言葉の輝く卵である」(『美貌の青空』p130)というように、詩刑、剥製、器、卵など、吉岡実の詩にまつわる単語が選ばれている。
③あるまとまったフレーズをお互いに関連のないまま文中に埋め込ませる技巧。フレーズの部分だけを切り取ると明瞭だし力強い。しかし文章全体としては意味不明である。少し離れたフレーズと呼応していたりするときもある。例を挙げると、「屋根からころげ落ちた時、口に碍子をくわえていた。これだけの理由で故郷を追放された男の、あの風呂敷を握った掌のことを考えると、途端に真黒こげになってしまう」(『美貌の青空』p148)。「屋根からころげ落ちた時、口に碍子をくわえていた」だけを取ると意味は通じるが、あととつながらない。しかし文末の「途端に真黒こげ」とは関連している。
④上記のような技巧は頭のなかで逐一考えたものではない。自然と口をついて出てくるもので、身に備わったもの。そういう意味では自動記述に近い。このイロジスムは落語家のしゃべり癖のような一種の話法であり、翻訳不可能なものである。ただし注意しなければならないのは、この話法には限界があることである。室伏鴻が「土方巽リーディング」で「即興では自分の身振りの基本的な習慣が繰り返されてしまう。これはシュールレアリスムの自動筆記でも同様」と指摘していたことは鋭い。
⑤土方巽は基本的に何かを直接伝えようとはしていない。初めから拒否している。相手(読者)にショックを与えることで、その言葉以外の言葉、あるいはイメージによって想像させ考えさせようとしているのである。明示しないで示唆している。「土方巽リーディング」でのインタビューでも、質問を絶えずはぐらかせようとしてインタビュアーを困らせているし、同書の対談で、室伏鴻が「あの人は“神秘化”の人でしょ」(p57)と発言しているように、生き方においても一種の韜晦癖があったようだ。それは彼が暗黒舞踏家という芸術の人であり、評論家とか実務家でないから許されるものだろう。もしこうした文章が財務省のお役人の手で書かれたものなら、たちどころに精神病院からお迎えが来ることになる(→これは差別表現だと思うがご海容を)。
⑥難解な文章ながら、全体としては何か言わんとするところが、おぼろげに伝わってくる。酒席の冗談交じりの談話や、友人あての心置きない手紙で繰り広げるアクロバットに近いものがある。一種の与太話であって、読者の方も真剣に捉えるというよりは、それを楽しんでいるという節がある。
そのほか気づいたところは以下のようなところです。
①舞踏家だけあって、「からだ」に関する言葉が多く、いくらでも例を挙げることができる。「人間、追いつめられれば、からだだけで密談するようになる」(『病める舞姫』p6)、「からだの中に溜まっている毛が溢れ出て髪の毛になったのだぞ」(『病める舞姫』p40)、「道端で膝の関節を外して涼んでいた私は」(『美貌の青空』p134)。
②同様に、抽象的なことが生身のからだを持ったり、動物や事物が人格を持ったりする。「道が襲いかかってきているのだ」(『病める舞姫』p102)、「そういうところに、現実が作男のようにのそっと立っているのである」(『美貌の青空』p88)、「スギナを噛む老人の顎を外せば、その辺の詳細を顎から聞くこともできるのではないか」(『美貌の青空』p137)、「もし箸に、『久しぶりだな。』などと声をかけられたらどうなることだろう」(『病める舞姫』p106)。
③自分のからだに関する離人症的な表現が面白い。以下すべて『病める舞姫』より。「身を沈めるようなやり方で、気の抜きとり方を練習していた。そしてそれをみみずに移すやり方で、自分のからだを立聴きするようにして、熱心にやっていたのだ」(p22)、「もう一つのからだが、いきなり殴り書きのように、私のからだを出ていこうとしている」(p60)、「その土の上に長く突き刺さった自分の影を耕したり掘り起こしたりしているのだった」(p69)、「その雪を履いて歩いてるような私が見える・・・雪むろに隠れようとして幽かな鬼となっている私が見えていた」(p193)
④珍しいことに、「演劇のゲーム性」や「遊びのレトリック」など、土方にしては比較的まともな文章がある。「演劇のゲーム性」は劇場論で、沈黙と観客の関係とか、俳優の心構えを説いており、「遊びのレトリック」は舞踏論でかなり具体的なことが書かれている。また、土方は意外とブッキッシュでもあり、「刑務所へ」では、バタイユ、ニーチェ、マルクーゼが引用されていた。根は文筆家に憧れていたのではないだろうか(いずれも『美貌の青空』所収)。
⑤『病める舞姫』は独立した作品で、土方巽の代表作だろう。ここに描かれている世界は、戦後間もなくの田舎の風景と切り離せない。これは今日のピカピカつるりとした21世紀の東京とは真逆の世界。土俗的で迷信的、貧困で、呪詛やまじないのようなフレーズに充ちている。
⑥全体が奇怪な言葉の宝庫となっている。これらを一枚の大きな画布に描けば、ボスの絵のようなものができあがるに違いない。
下手に解説を続けるよりは、より多く現物に接した方が有意義と思うので、大量になりますが、引用しておきます。
私は何者かによってすでに踊らされてしまったような感じにとらわれた/p8
そういうものを食べているとどういうわけか、家の中から痩せた男がちょろちょろと出てきて、裏の畑に鍬を入れ、葱を抜いたりしていた/p11
泣いているものと溶けているものの区別がつかなくなり/p12
ともかく、影が光に息をつかさせているような塩梅が好きだったのであろう/p15
クレヨンが濡れた板と馴染まないのか、描かれた兎の絵が板の上を滑っていく/p34
骨抜きになった人の影を自分のからだに立て掛けていた/p82
粥っ腹のせいか湯づけ飯のせいか、鼻から白い小骨が少し出かかっているその男は、舌を出して包丁に積もったざらめ雪を啜るのだが、そのへんのことは少し省略したい/p167
「・・・お前がよく家のなかで喰わされる米の粉団子は、あれは嘘つきだ。」そう言われてみると、確かにその団子にも恥じるような色があった気がする/p183
以上、『病める舞姫』より
股暗がりにチラチラと焚付けて来るものがあって、そんなところからチョロチョロと毛が生えて来たように想われる/p50
私は真に、劇場においては腰が砕けた観劇法こそ望ましいものだと考えている。関節が折られ、脛が斤で計られる桟敷でこそ、蚤にアッパーカットを喰わせられるからである/p56
猫の死骸よりも美しいものがある/p63
子供の遊びには危険が一ぱいである。追跡していた子供が自分のからだに追跡されてしまい、追跡が追跡を追っかけて、変に明るくなってしまってドブにはまったりするのだ/p72
目をかけてやった記憶もないのに、庭に来て坐っているものがある。「夏だな」/p72
こういう印鑑体が近づいてくると、子供達はなぜか泣くことを覚えるのである。判コと入れ代って死体が風にまで目鼻をつけようとして迫ってくるのだから、なんとも怖いのだ/p80
わざと誤って鶏を叩く正しい計算/p82
からだの中に住所を持っている人が表札を表に曝すとき/p82
舞踏する器は、舞踏を招き入れる器でもある。どちらにせよ、その器は絶えずからっぽの状態を保持してなければならない・・・死骸も退屈な時間を嫌って、このからっぽのなかに移体してくる/p93
人前ではめったに見せないが、表を歩いていると急に猿の顔つきになる時がある。この表情に気付き始めたのは、七つ八つの頃からではないだろうか。この顔は何を考えているのか、手もまた忙しくなってくるのだ。こんな自分をどんな魂胆があるのか、私はお菊さんと呼んでいた/p104
酒席で私が、なんだろうと思って目を上げてみると、まったく素面の彼の頭上で、髪の毛だけが盛んに酔っているのを見かけることがしばしばある/p157
以上、『美貌の青空』より



















 左の作品の版木
左の作品の版木

