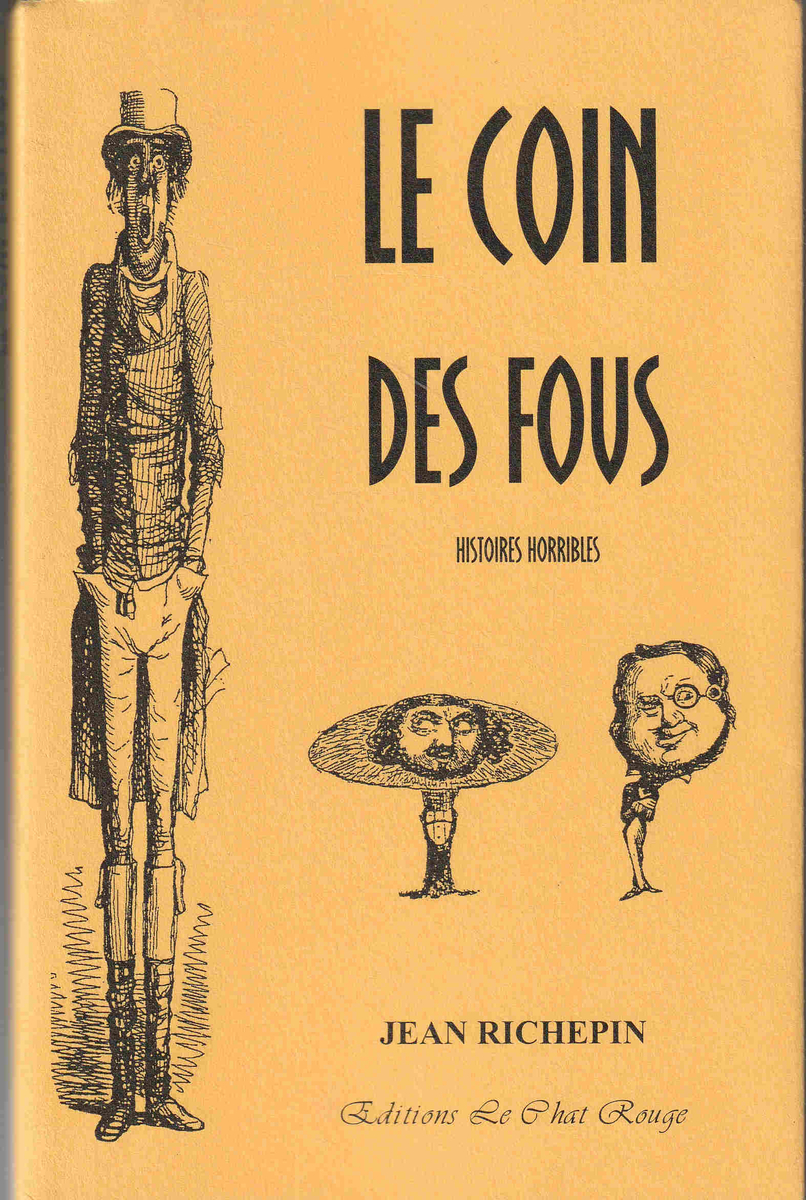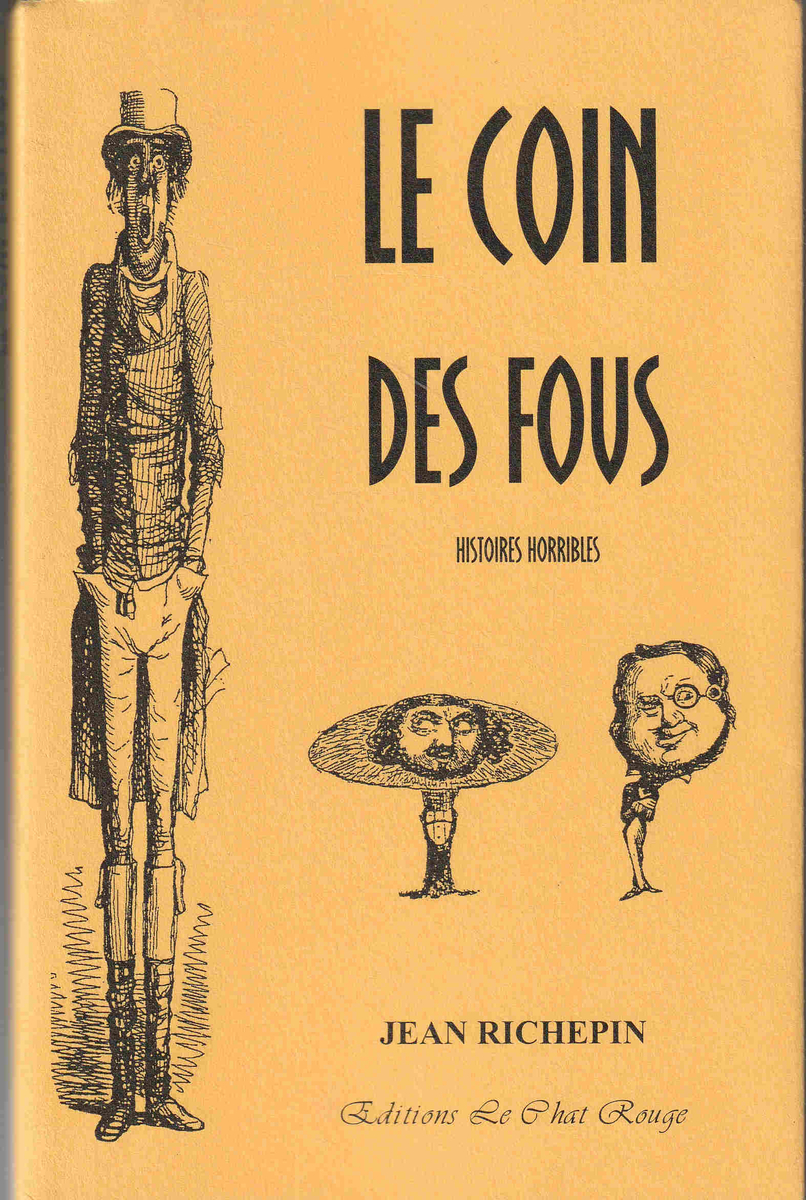
JEAN RICHEPIN『LE COIN DES FOUS―HISTOIRES HORRIBLES』(Le Chat Rouge 2011年)
タイトルは、「au coin de feu(炉辺で)」をもじっています。前回読んだ『Les morts bizarres(風変わりな死)』よりはよくできていて、まだリシュパンは3冊しか読んでませんが、いちばんの傑作集。ジェラルド・ドゥシュマンの序文によると、初出は1892年から1900年に雑誌に掲載されたもので、ページ数があらかじめ決まっているので、みな同じぐらいの長さ。その制約が功を奏したのか、叙述が簡潔で脱線が少なくて、読みやすい。
題名どおり、狂気のさまざまな様態が描かれています。アッシリア魔術の研究に没頭しすぎて大学教授の職を追われた老人、嫉妬に狂って妻を病気にさせる医師、からくり時計を復元するために自分を犠牲にする時計師、古代探究が昂じ狂気を感じさせる学者、自分のなかの敵と戦い遂には殺してしまう自殺者、傑作をものするために悪魔と取引をして死んでいく老画家、鏡の表面に幻覚を見る若者、猿のような二体のミイラを天使のミイラと言う冒険家、肖像画の眼の光に精神を病んだ精神科医、恋人の頭部を手提げ金庫に入れて持ち歩いているロシアの零落貴族、2年ごとにフランス人とイギリス人とに人格が入れ替わる若者、五感を摩耗させ超感覚を手に入れたと信じる修行者、患者の狂気に伝染した精神科医、行者から遠くインドの地にペストを生じさせるのを見せられ夢か現実か分からなくなった男など。
真剣さが昂じて妄想に陥っていく人物、あるいは狂気と紙一重の人物が登場し、読者も語り手の妄想か現実か分からなくなってしまいますが、そういう曖昧な状態を作り出すのに、三人称的叙述のなかに、二人称的な会話や、一人称的語りがあったり手紙の告白があったりする物語という形式がとてもよく合っているのだと思います。全般的な傾向としては、学者が狂気に陥ってしまう探究(妄想?)の激しさ、患者から医者に伝染する狂気の強さが描かれるものがいくつかあり、また序文でも指摘されていたように、視線に捉われたり、眼によって催眠状態が引き起こされるなど、眼が鍵となる話が多くありました。
23の短篇が収録されていますが、なかでも佳篇は、「Le perroquet(鸚鵡)」「Le peintre d’yeux(眼の画家)」「Le miroir(鏡)」「Booglottisme(牛舌症)」「La cité des gemmes(宝石の町)」「L’homme-peste(ペストを作る男)」、次に、「Lilith(リリス)」「L’horloge(時計)」「Les deux portraits(二つの肖像画)」「Fezzan(フェザン)」「Les autres yeux(他人の眼)」「Le regard(眼差し)」「Le coffre rouge(赤い金庫)」「l’autre sens(超感覚)」でしょう。簡単に概要を記しておきます。
〇Lilith(リリス)
貧しい若者二人は、毎夜、老人が庭で奇妙な振る舞いをし「リリス!」と呼びかけるのを聞いた。調べてみると、老人は元大学教授だが、アッシリアの魔術の研究に没頭し、精神異常とみなされて退職させられていた。著書を読もうとしたが解読不能で断念した。が40年後、仲間で魔法でも使ったと思われるぐらい大成功した男が、その老人の孫娘と結婚していたことを知る。話の運びが巧み。
Un legs(遺産)
父の古くからの友人から突然遺産を譲られ、遺書を受け取りに行く主人公。父の友人は醜男で愚鈍で薮医者と言われていたが、親の莫大な遺産を受け継ぎ、医者を辞めて地方いちばんの美女と結婚していた。がその家は庭師が次々結核で死ぬという噂だった。はるばる訪ねて行くと、美人の妻も半年前に死んでおり、遺書には狂気の医者による恐ろしい犯罪が告白されていた。
〇L’horloge(時計)
悪魔が作ったという伝説のある教会のからくり時計を復活させようと、現代の時計師が他の時計を放ったらかしにして教会に閉じこもり、町中から気違い呼ばわりされていた。最後の重石一つがどうしても見つからず日々が過ぎていたが、ある日鐘が鳴り、時計が動き始めた。町中が賛辞を送ろうと時計師を探すと、自ら重石となるため時計の鎖で首を吊っていた。
◎Le perroquet(鸚鵡)
ある研究者の遺贈品を一式買ったが、それは、バスク研究者の友人が喜ぶと思った論文だけが目当てだった。骨董商がしつこく鸚鵡も一緒にと勧めたが、そればかりは断った。マデイラに滞在していた友人に送ると、すぐ電報が来て、鸚鵡はどこだという。論文によれば、アトランティス語を喋る貴重な鳥で、アトランティスがアメリカ原住民とバスクの両方に繋がることを証明できる存在だという。二人で骨董商に駆けつけるが、骨董商は鸚鵡は意味不明の言葉ばかり喋るので殺したと告げられる。話の運びが絶妙。
〇Les deux portraits(二つの肖像画)
主人公が骨董店で見かけた二つの肖像画。互いに憎しみに満ちた目で見つめ合っていた。ロンドンである裁判で有名になった貴族の夫婦だという。イギリスへ行く機会があり、調べてみると、夫人の浮気相手を撲殺した夫が半年後夫人に毒殺されたという事件だった。パリに戻り店に肖像画を見に行ってみると、絵を落としたため、二作品とも顔や目に損傷ができてしまったという。絵には魂が宿ると言うが単なる偶然か。
L’ennemi(敵)
ただならぬ気配の男が来院し、敵がいつも自分のしようとすることを妨害し、迫害すると訴えてきた。気違いのようだが、聞いてみると、恋をしてもその女を嫌いになるように仕向けたり、食べようとした料理に唾を吐きかけたりするという。決闘か、裁判か、最悪殺すんですなと言ったところ、男は大喜びで、殺すんだと叫んで出て行った。その夕、男から敵を殺したから見に来てくれとメモが来た。行ってみると、男は自分の胸を撃ち抜いていた。
Duel d’âme(魂の決闘)
何世代も続く予審判事の家系に生まれ将来を嘱望されていた予審判事のところに、何世代も犯罪者の家系だという男から、決着をつけよう、無実の人を死刑台に送るようにしてやると挑戦状が来た。単なる狂人のたわ言と無視していたが、その後、悪魔の策略が感じられるような複雑な事件が増えた。ある事件で犯人を死刑台送りにした後、お前は無実の男を罰したから私の勝ちだ、と手紙が来た。それで判事を辞める決心をした。
◎Le peintre d’yeux(眼の画家)
フランドル派の今は亡き画家に1作だけ大傑作があり、年1回万聖節に1時間だけ開帳される。画家は信心深い3児の父親として、友人や弟子たちから慕われていたが、心底では真の傑作をものしたいと念じていた。ある日見知らぬ男が眼の描き方を教えようとやって来て以来、画家は人を寄せ付けず画室に閉じこもるようになり、最後に描き上げた自画像の前で死んでいた。見知らぬ男は悪魔で、絵が完成すると同時にモデルが死んでしまうと言われ、自画像を描くことにしたという。悪魔と取引をする芸術家譚。
◎Le miroir(鏡)
骨董店で奇妙な鏡を手に入れた若者。縁がなく鉛の板が貼りついていて、ゴチック文字で詩が書かれていた。翻訳で読むと、生きながら水の中に閉じ込められ、美しい王子様に助けられるオンディーヌが歌われていた。その詩を読んで鏡を見つめていると、奥の方に次第にオンディーヌの顔が見えてきた。ぼんやりと声まで聞こえて…。がある日若者は鉛の板を抱えた溺死体となって発見された。オンディーヌは解放されたのだろうか。導入部のファンタジックな美しさ。結局語っているのが誰か分からない面白さもある。
〇Fezzan(フェザン)
世界中を旅している友人のところで、リビア砂漠の記念品を見ていると、黒人か猿か男か女か分からない二体のミイラの写真があった。何かと訊ねると、それは天使の写真だと言って、現地で体験した話を語る。熱病で衰えた筋肉を復活させる呪術師だという二人の老姉妹に天使のようなマッサージをされたと言うのだった。出だしの語りはとても魅力的だったが、後半尻すぼみ。
〇Les autres yeux(他人の眼)
神父が諭したにもかかわらず、「他人の眼」で魂を見ようとした若者。眼前に見えたのは、腐った臭いを放つキノコや毒液を吐く蛇の凝集したような恐ろしい潰瘍で、七つの大罪を象徴するものだった。誰の魂だ?神父お前のか?と、手にした斧を振りまわしたところ、鏡が割れた。自分の魂だったのだ。
〇Le regard(眼差し)
精神科医が一人の狂人の説明をするが様子がおかしい。その患者は、骨董店で買った肖像画の眼の中に、古代の黄金都市の遺跡が見えると言っており、たしかに肖像の眼は生き生きした金色の光を放っていて精神がおかしくなるから絵を切り刻んだと医師は言う。が医師の眼には狂気の光が宿っていた。医師が出て行った後、机の上を見ると切り刻んだという肖像画の眼の部分が保管されていた。精神科医もおかしくなっていたのだ。
〇Le coffre rouge(赤い金庫)
ロシアの零落貴族が肌身離さず持ち歩いている赤い金庫。大泥棒の俺様が盗んでやると、情報を集めると、その貴族は賭けで無一文になっている筈だと言う。何か貴重なものが入っているに違いないと、ますます意欲が湧き、貴族に近づいて友人になり一緒に住むようになり、催眠薬を飲ませて、いよいよと金庫を開けると、そこから出てきたものは、逆に心を盗まれるような前代未聞のものだった。
En robe blanche(白無垢で)
編集室での一コマ。若手が恋の手柄話を話すなか、武骨で醜い編集長が、若かりし頃の少女との思い出を語る。少女から告白され逃げまわっていたが、ある晩家に帰ると、その少女がベッドで待ち構えていて、抱いてくれないと窓から飛び降りると迫られたという話で、結婚式に着る白い服を着ていたという。
Le cabri(子ヤギ)
ロシアの寡婦の伯爵夫人が色目を使っているのに、なぜお前は避けようとするのかと、ロシアの士官が聞くと、「子ヤギのせい」との返事。聞けば、その男が昔飼っていた子ヤギの眼が反り、唇が山形になっていたが、それは不幸をもたらす印と山羊飼いに言われたという。伯爵夫人も同じ特徴を持っていたのが理由だった。実際、5人の先夫が変死していた。
◎Booglottisme(牛舌症)
トルコの港で、夜、金もなく港に降ろされた若者が、黒人に金貨を握らされ、まだあるよと言われるまま迷路のような小道を通って連れていかれたのは、裸の女がベッドに横たわる部屋だった。顔には革の面が嵌められ、キスもできず一言もしゃべらない。ただ吐息が洩れるだけ。狂ったような愛を交わし、朝黒人が迎えに来て船に乗ると、医者が牛のような舌を持つ女性の症例を話しているのを耳にした。ポケットを探ると金貨がザクザクと唸っていた。ロチの短篇のような東洋趣味の味わい。浦島太郎を卑小にしたような桃源譚。
Le masque(仮面の男)
いつも仮面をはずさず、長年雇われている使用人も顔を見たことがないという。情婦も顔を知らず、かつてその男がインドにいたときも仮面をしていた。顔が醜かったからか、いやそうではない美し過ぎたから。ただ一人仮面の男の死に立ち会った医師が素顔を見て、ギリシア神話の神を見たかのように、目が眩み、足が震えたという。
Les sœurs Moche(醜い姉妹)
田舎には小説のネタがあるよと、田舎に残っている友人が、われわれが子どものころよく大声で叱られた老姉妹の話を持ち出した。皺だらけの萎びた魔女のような顔で、髭も生えていたのをよく覚えていた。が実際は信心深く貧しい人たちに施しをする人たちだったと記憶している。友人は二人が一緒に自殺をしたんだと言いながら墓に案内する。そこには二人の男性名が書かれていた。
L’âme double(二重の魂)
2年ごとに、フランス人とイギリス人の二つの人格を交互に生きる若者。片方の2年間の記憶はまったくない。フランスの医者が相談を受け、2年近くの観察の結果、二重人格者と結論づけようとしたところ、突然失踪し、イギリスの医者に手柄を奪われた。が若者も二重人格と知って自殺したので、科学的知見は永久に失われたと嘆く。
〇l’autre sens(超感覚)
心理学と哲学の融合を目指し、チベットの聖者の所へ修行に向かった哲学者。五感を減耗させることで、超感覚を得られるのではないかというのが目的だ。友人のもとへ届いた手紙が公開されるが、最後の手紙には修行が成功し、新しい超感覚を得たと書かれていた。だが、その手紙には、「五感を減耗したという妄想の重篤な精神病者が入院した」という精神病医のメモがついていた。どちらの言い分が正しいのだろうか。
◎La cité des gemmes(宝石の町)
もう二人もおかしくなったほど伝染性のある狂人だから気をつけてと精神科医は注意を促した。その狂人は鉱物、科学の知識を持った穏やかな学者で、人工的に宝石を作る技術について語り、すでに古代エジプトでそれが成功していて、宝石の町まであったと、滔々と語る。面会を終え、医師と話をした主人公は、医師にもすでに狂気が伝染しているのを見てとり愕然とする。
◎L’homme-peste(ペストを作る男)
ロンドンから離れたことのない友人の挿絵画家がインドのペストの猖獗の様を描いて評判になった。見たままを描いただけさと答える画家について行くと、ある居酒屋の一室で、ヨガ行者からまったく同じペストの光景を見せられる。後日、インドの新聞にペストが突然猖獗を極めたという記事が出たことを知るが、発生日時が居酒屋で見た日時と同じだった。たしかに見たんだが、あれは夢だったのだろうか。
Le nouvel explosif(新しい爆発)
主人公が友人に、宇宙進化論について弁舌を振るい、いま集中化の時期で、まもなく爆発期に入るからちょっとした衝撃で爆発するだろうと言うと、友人はそれを起こせる人物を最近精神病院から退院させたから紹介しようと言う。狂人と二人きりで会うと、確かに狂人の眼をしていて、公園の大石に何かを塗りつけて爆発させた。友人に後でそれを話すと、よくできた笑劇だと笑う。